
JOHNS35巻2号
【特集】わかりやすく伝える インフォームド・コンセント
【特集】わかりやすく伝える インフォームド・コンセント

小児内科51巻2号
【特集】小児の気道感染症─症状からどこまで原因を探れるか?
【特集】小児の気道感染症─症状からどこまで原因を探れるか?

腎と透析86巻2号
【特集】マグネシウム代謝―その新たな臨床的意義
【特集】マグネシウム代謝―その新たな臨床的意義

看護管理 Vol.29 No.8
2019/08/09
特集 対話のプロセスを支援する倫理カンファレンスの技法 ジレンマ・メソッド
特集 対話のプロセスを支援する倫理カンファレンスの技法 ジレンマ・メソッド 近年,ACP,意思決定支援が注目されており,各施設で臨床倫理に関する取り組みが加速しています。臨床倫理上の課題については,最終的には当事者間で話し合い,その患者にとっての最善の判断を導く必要があります。これまでさまざまな事例検討の枠組みが試されてきましたが,情報整理のツールとしての意味合いが強く,多職種間で検討するための話し合いや対話の方法を具体的に示すものはありませんでした。本特集で取り上げる「ジレンマ・メソッド」は,対話のプロセスを支援する構造化された倫理カンファレンスの技法です。事例提供者の問題意識,困りごとに焦点を当てて話し合いを進めます。誰かに特権的な権威を認めず,困難事例に関わる全ての人が共に考えるための具体的な道筋を示すものです。組織やチームに対話の文化をつくることにも期待できます。本特集では詳細な解説と模擬カンファレンスの採録記事を通じて,その全体像と臨床にもたらす価値を紹介します。

総合リハビリテーション Vol.47 No.8
2019/08/09
特集 摂食嚥下リハビリテーションの未来 各専門職に何ができるか
特集 摂食嚥下リハビリテーションの未来 各専門職に何ができるか 摂食嚥下障害は多くの患者・高齢者にみられる症状であり,病院,施設,在宅,擁護教育の現場など あらゆる臨床場面で,摂食嚥下障害への対応が行われています.リハビリテーションに関連するどの専 門職種の業務のなかでも,摂食嚥下障害に対応することが重要な部分を占めつつあります.そこで,日 ごろは注目されることの少ない理学療法士,作業療法士も含めた,各専門職の方々に,その職種におけ る摂食嚥下障害分野への取り組みについて,どのような特色を有し,力を発揮できるのか紹介いただき ました.今までは,「摂食嚥下障害は自分とは関係ない」と考えていた方も,ぜひ自分の職域のなかで, 摂食嚥下障害に対応していただけると幸いです.

生体の科学 Vol.70 No.4
2019年08月発行
特集 メカノバイオロジー
特集 メカノバイオロジー -

臨床整形外科 Vol.54 No.8
2019年08月発行
誌上シンポジウム 整形外科治療の費用対効果
誌上シンポジウム 整形外科治療の費用対効果 -

medicina Vol.56 No.9
2019年08月発行
特集 みんなが知っておきたい透析診療 透析のキホンと患者の診かた
特集 みんなが知っておきたい透析診療 透析のキホンと患者の診かた 透析患者数の増加に伴い、外来で透析患者を診る機会はますます多くなっていくと思われる。しかし、透析患者には診療上、注意すべきことが数多く存在し、特に透析専門医がいない施設では、内科医も透析の知識を身につけておくことが必須である。本特集では透析の基本を踏まえたうえで、どう診ればよいのかを解説する。

実験医学 Vol.37 No.14
2019年9月号
【特集】HLAと疾患感受性
【特集】HLAと疾患感受性 免疫学的な自己を規定する分子HLA.免疫系の疾患のみならず様々な生活習慣病のリスク因子と関与していることも明らかに.HLAの基礎から研究の歴史,さらにHLAから見えてきた疾患発症機構までお届けします.

臨牀透析 Vol.35 No.9
2019年8月号
標準血液透析を再考する-最良の透析処方・管理技術とは
標準血液透析を再考する-最良の透析処方・管理技術とは
透析患者の高齢化は進み,合併症の多様化もみられている.今日では一人ひとりの透析患者の病態を正確に把握したうえで最良の透析処方を実践することが重要と考えられている.

腎と透析86巻1号
2019年1月号
【特集】慢性腎臓病における心血管障害
【特集】慢性腎臓病における心血管障害 慢性腎臓病における心血管障害

消化器内視鏡31巻1号
2019年1月号
【特集】エキスパートへの道─上部消化管
【特集】エキスパートへの道─上部消化管 エキスパートへの道─上部消化管

小児内科51巻1号
2019年1月号
【特集】人工知能(AI)と小児医療
【特集】人工知能(AI)と小児医療 人工知能(AI)と小児医療

小児外科51巻1号
2019年1月号
【特集】新生児外科疾患の精神・身体発育
【特集】新生児外科疾患の精神・身体発育 新生児外科疾患の精神・身体発育

周産期医学49巻1号
2019年1月号
【特集】胎盤・臍帯・羊水を再び考える
【特集】胎盤・臍帯・羊水を再び考える 胎盤・臍帯・羊水を再び考える

JOHNS35巻1号
2019年1月号
【特集】ビギナーのための耳鳴・聴覚過敏診療
【特集】ビギナーのための耳鳴・聴覚過敏診療 ビギナーのための耳鳴・聴覚過敏診療

32枚のカルテ
医療現場の診療ディテール×32事例
■32枚のカルテ。32人の患者。32の疾患と病態。32の診断と治療。32の経過と予後。そして32の人生―。
■医療現場の診療の実際を,2人の医師―内科医と外科医が詳細に描出。診察から検査,投薬,処置,手術,予後に至るまでの診療のディテールと,その折々の医師の思考過程や感情の動きを,臨場感溢れる筆致でリアルに再現。診療の実際を知り,深い医療知識を得ることができます!!
■各話ごとに請求のプロによる「レセプト・医療費の原風景」も付記し,個々の診療行為が実際にどう保険請求されているかをわかりやすく解説してあります。請求上のポイントが詳解されており,請求業務にも役立ちます。
■臨床研修医,看護師,コ・メディカルの方にも臨床知識習得に最適な1冊です!!
★傷病名,手術術式,検査等,専門用語のわかりやすい解説付き。
★巻末の約460項目の索引で,読みたい症例が簡単に検索可能。
「Kokutai」(04年12月号),「社会保障」(04年12月13日号),「看護管理」(05年1月号),「日経メディカル」(05年1月号),「メディカル朝日」(05年2月号),「ばんぶう」(05年2月号),「ジャミック ジャーナル」(05年3月号),「看護学雑誌」(05年5月号)

腰痛をめぐる常識の嘘
腰痛の治療に携わっている人々が、この本で刺激を受け、腰痛に興味を持ち、研究心が刺激されることを願って執筆されたもの。

患者応対マナーBOOK
言葉と態度は“処方”である
■病院・クリニックの全スタッフ(事務職員・看護婦・医師・コメディカル)のための患者接遇マナーの基本と応用を,多数のイラストを用いて的確にわかりやすく解説しています。
■「院内イメージ度自己診断チェック・リスト」や,「医療事故等を防止するための院内活動のあり方」,「個人情報保護法の取扱い」も収録!病院・クリニックの職員研修や,医療事務専門学校・看護学校の教材としても最適です。
■(1)患者に対する言葉づかいと接遇態度の基本,(2)窓口での具体的な患者応対法,(3)電話の受け方・かけ方,(4)外来診察の場での患者応対,(5)病棟での患者応対,(6)エレベーター等でのマナー,(7)職場での人間関係とルール・エチケット(8)仕事の指示や報告の仕方─など,医療現場で必要不可欠な全応対方法を満載。完璧にマスターできます。
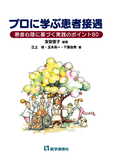
プロに学ぶ患者接遇
患者心理に基づく実践のポイント80
■患者さんの心理を徹底的に分析して理解を深め,そのうえで部門ごとの具体的応対方法について解説。接遇入門はもちろん,スキルアップにも最適です。
■具体的事例・会話術を随所に散りばめ、接遇のプロに必須の80のポイントを抽出しています。
■患者応対マナーにとどまらない真の患者接遇が身につき,あらゆる場面に実践応用が可能です。
主要目次
●医療場面における患者接遇●患者接遇の基本的考え方●患者の心理と接遇:「専門家」と「病にかかった人」の間にある溝/患者さんの心理●医事課における患者接遇サービス:病院の中の医事課/医事課窓口の役割と応対/電話応対/実践上の注意したいポイント30●看護場面における接遇:看護における接遇とは/今後の医療における看護の位置付けと接遇/看護者が実践する接遇とは●医師部門での患者接遇―インフォームド・コンセントの実施と手順―:ICの概念とその背景/ICの実施とすすめ方/癌診療におけるIC●患者に選ばれる病院は接遇から―他
