
「医療4.0」を支える 医療産業イノベーションの最前線
東京大学公開講座「医療産業イノベーションフォーラム」より、医療産業の最前線を産官学のフロントラインに立つ専門家が提言!
「医療産業イノベーションフォーラム」では、医療産業を巡る産官学のトップランナーを講師に招き、世界のトレンドを捉えつつ、日本が抱える問題点の抽出とブレークスルー実現を目指している。
本書では、再生医療とデジタル技術×医療産業を論ずるとともに、そのエコシステムに光を当てます。さらには、医師であり医療系ベンチャーを立ち上げたアントレプレナーを例に、現場で挑戦を続ける医療従事者の問題意識を通して、医療と社会の将来像を描く取り組みを紹介します。

日経DIクイズ 呼吸器疾患篇
月刊誌「日経ドラッグインフォメーション」の人気コラムから、インフルエンザ、感冒、結核、気管支喘息、COPDなど、主な呼吸器疾患のクイズを厳選 疾患の基礎知識を学びながら、薬剤関連の理解を深めるコンセプトの「日経DIクイズ 疾患篇」。
「呼吸器疾患の基礎知識と処方の実際」で、気管支喘息、COPD、肺炎、小児の呼吸器感染症など、代表的な呼吸器疾患の病態生理と治療指針の基本を学びます。そして「日経DIクイズ」で、これら呼吸器疾患の服薬指導や疑義照会のコツについて、クイズ形式で理解を深めていきます。
薬物療法を含めた診療ガイドラインの改訂、薬剤の適応追加、後発医薬品の情報など、現状に則して内容をアップデートしています。
現場で働く薬局薬剤師にとって、患者指導のための基礎学習から知識のレベルアップまでをスムーズに学べる一冊です。
●呼吸器疾患の基礎知識と処方の実際(インフルエンザ、小児呼吸器感染症、成人市中肺炎、結核、小児気管支喘息、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺癌薬物療法における支持療法)の8疾患を臨床医が解説
●呼吸器疾患に関するクイズ 厳選40題

≪【あめいろぐ】シリーズ≫
あめいろぐホスピタリスト
“Ameilog” book on hospitalist
アメリカの最新医療情報とともに日本の臨床を考える「あめいろぐ」シリーズ第2弾のテーマは「ホスピタリスト」。ホスピタリストは、病棟急性期の入院患者を一手に引き受け、内科全般をバランスよく診療し管理する仕事で、病棟勤務医・病棟専属医・病院内総合医などの名称があります。米国では、外来患者は総合診療医(慢性疾患)と救急医(急性疾患)が、内科入院患者はホスピタリストがそれぞれ対応し、外来と病棟マネジメントの分業化をしています。日本でも日本版ホスピタリストの確立が着目されており、病棟管理と総合内科診療のエキスパートであるホスピタリストの働きにより、「無駄な検査」や「不要な長期入院」を抑えることが期待されています。今後、ホスピタリストの導入によって「医療の質」・「患者満足度」・「医師の働き方」が様変わりするかもしれません。研修医・医学生などの初学者だけでなく、現在第一線で活躍されているすべての医師におススメする書籍です。

≪【あめいろぐ】シリーズ≫
あめいろぐ予防医学
“Ameilog” book on preventive medicine
在米日本人医療従事者による情報発信サイト「あめいろぐ」を書籍化。日本とアメリカの臨床を経験した若きエキスパートが、「米国のここがスゴイ」「日本のここがいただけない」「米国のここはどうか」「日本のここは際立っている」など、比較文化論的な視野から、臨床に役立つ本音ベースのノウハウを語ります。シリーズ第1弾「予防医学」では、総監修の反田篤志医師が「キレッキレッ」の論旨を展開。

ポイントで学ぶ科学英語論文の書き方 改訂版
科学者・技術者にとって、英語で論文を書き論文誌に発表することは、研究・開発そのものと同じくらい重要な作業ですが、英語論文は、才能ではなく技量(skill)です。どのように書くかの知識をもつと同時に、書く練習をしなければなりません。適切な指導によって導かれればさらに効果が上がると、著者は述べます。 つまり、コツを押さえて適切な訓練をすれば、英語の表現力を修得でき、英語圏だけではなく、世界の研究者や技術者に的確に理解される論文が書けるようになります。 そのために、「英語の論理」に沿って「英語的発想」で英語論文を書くことが重要です。本書は、2001年に出版された『ポイントで学ぶ 科学英語論文の書き方』の改訂版です。著者は、それをもとに講義ノートを作成し、「英語論文の書き方」の講義をする中で、日本人理工系学生の英語・英語論文の書き方の弱点を見つけ、著者自ら執筆した英語論文をネイティブの添削を受けて学んだ内容などを新たに含んだ一冊となっています。

見えない悲しみをみつめて
内的対象喪失
「内的対象喪失」は、思い通りにいかない、満たされないという、その人の中でおこっている失われた感覚です。本書では、特に親子のテーマ、心身症状を取り上げ、内的対象喪失が心身に及ぼす影響と、失った大事なことに気づき受け入れるためのプロセスについて、症例を通しわかりやすく解説しています。
失った心に精神療法(心理療法)はどのように関わりうるのか―医療や臨床心理の専門家、さらには一般の方にも、おすすめの1冊です。

リアルワールド・プラクティス
ポケット版 改訂 せん妄の臨床
「せん妄の臨床 リアルワールド・プラクティス」待望の改訂版!
せん妄に対する最新の知見を網羅しつつ、著者のこれまでの臨床経験から現場での具体的な対処法がイメージしやすいようにまとめた1冊。症例編では臨床判断が求められるポイントでClinical Questionを設け、こういうときどう対処するか、考えながら読み進めることができる。
改訂版では、せん妄の予防的介入や、精神科医だけでなく看護師を含む医療スタッフのチームとしての取り組みについても言及した。

漢方外来 ナンパ術
患者さんを増やしたい人、外来がうまくなりたい人、必読!
まったく診療スタイルの異なる3人の外来診療の達人にはそれぞれのナンパ術がありました。外来好きの先生は何が違うのか、患者さんで溢れた繁盛する外来はどこが違うのか。人気の秘密を披露します!

サポート医療・副作用軽減・緩和に
フローチャートがん漢方薬
がん診療の進歩はすばらしく、現在では治せるがんも増えています。しかし、ひとたび「がん」と診断されれば、患者は肉体的にも精神的にも厳しい状況に置かれます。そのようなときに漢方薬でまず闘う気力をつけるように、そしてがんと闘うためにできることをたくさんすれば、奇跡が起こることもあると、そのように希望をつなぐことがなにより大切です。そんな医療の実践に、ぜひ漢方薬をお役立てください。おなじみのフローチャート形式で漢方ビギナーでも簡単に処方選択ができるように解説しました。モダン・カンポウは、「西洋医のための漢方」をわかりやすく提案しています。本シリーズをお読みになっていない先生でも無理なく漢方が処方できるように配慮してあります。漢方薬を西洋医学の補助として取り入れ、がん診療の幅を広げましょう。
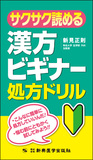
サクサク読める漢方ビギナー処方ドリル
まずはともかく300例に処方してみましょう。それで漢方がどんなものかつかむことができます。本書は西洋医学を専門とする先生方のための漢方薬処方のスタートブック。患者さんの訴えを聞いて、自分ならどんな処方をするか挑戦してみてください。読み進むうちに処方選択のキーワードを獲得することができます。まずは患者さんの訴えと醸し出す雰囲気から処方選択の方法を学び、明日の臨床にお役立てください。

レジデントノート増刊 Vol.21 No.8
【特集】ホスピタリスト直伝!入院診療 虎の巻
【特集】ホスピタリスト直伝!入院診療 虎の巻 入院から退院までにいつ,何を行うべきかをまとめた本書.入院診療で大事なことが全部わかり,自信を持って担当医になれる!また,患者とのトラブルの適切な対応のしかたや改善につながるカンファの進め方も紹介!

≪Crosslink 理学療法学テキスト≫
神経障害理学療法学Ⅱ 神経筋障害
理学療法学専門科目に対応し,講義・実習・臨床まで広く長く活用できる新テキスト。
各巻は,単なる丸暗記するための知識ではなく,なぜその評価法・治療法を選ぶのか,もしくは選んではいけないのか(禁忌)など根拠を示しながら,臨床につなげられるよう具体的に解説。平易な表現を用いながらも詳しく記述した本文と,図表を多用した紙面で理解しやすい構成となっている。
各見出しごとに「POINT」を設けて重要事項をまとめ,どこに重点を置いて学習すべきか,一目でわかるようになっている。また,さまざまな角度からの情報を盛り込んだ囲み記事も充実。巻末には症例検討や実習で役立つ「症例集」をまとめて掲載し,国家試験合格を最終目標とするだけでなく,臨床実習やその先の臨床の場でも活用できるつくりとなっている。
本巻「神経障害理学療法学Ⅱ 神経筋障害」では,総論で中枢神経系の基礎知識について解説し,各論でパーキンソン病,脊髄小脳変性症・多系統萎縮症,筋ジストロフィー症,筋萎縮性側索硬化症,多発性硬化症,多発神経炎・ニューロパチー(ギラン・バレー症候群など),末梢神経損傷(腕神経叢損傷・絞扼性末梢神経損傷),脳性麻痺の理学療法について解説している。

≪Crosslink 理学療法学テキスト≫
神経障害理学療法学Ⅰ 脳血管障害,頭部外傷,脊髄損傷
脳血管障害,頭部外傷,脊髄損傷
理学療法学専門科目に対応し,講義・実習・臨床まで広く長く活用できる新テキスト。
各巻は,単なる丸暗記するための知識ではなく,なぜその評価法・治療法を選ぶのか,もしくは選んではいけないのか(禁忌)など根拠を示しながら,臨床につなげられるよう具体的に解説。平易な表現を用いながらも詳しく記述した本文と,図表を多用した紙面で理解しやすい構成となっている。
各見出しごとに「POINT」を設けて重要事項をまとめ,どこに重点を置いて学習すべきか,一目でわかるようになっている。また,さまざまな角度からの情報を盛り込んだ囲み記事も充実。巻末には症例検討や実習で役立つ「症例集」をまとめて掲載し,国家試験合格を最終目標とするだけでなく,臨床実習やその先の臨床の場でも活用できるつくりとなっている。
本巻「神経障害理学療法学Ⅰ 脳血管障害,頭部外傷,脊髄損傷」では,中枢神経系の基礎知識に続き,脳血管障害,頭部外傷,脊髄損傷それぞれの病態,症候・障害,医学的検査,医師による治療,理学療法評価および治療手技について解説している。

短期集中!オオサンショウウオ先生の
糖尿病論文で学ぶ医療統計セミナー
疫学研究・臨床試験・費用効果分析
実論文4本を教材に,本物の統計力を磨く!疫学データによるモデル構築から費用効果分析まで,全26講+演習問題で着実に学べる.1講1講が短いのでスキマ時間に受講可能.糖尿病にかかわるすべての診療科に!

ICUから始める離床の基本
あなたの施設でできる早期離床のヒケツ教えます!
ICUで離床を始めたい医師やメディカルスタッフ必携!患者の社会復帰をめざした早期離床プロトコールを大公開.離床を行うためのしくみ作りから実践的スキルまで,対話形式でやさしく楽しく学べます!

リハの現場でこんなに役立つiPhone活用術
セラピストのためのiPhone・iPad活用本が登場!臨床を,研究を,勉強を…ちょっと楽しく,便利にする使い方をご紹介!アプリに使われるのでなく,アイディアで使いこなすための1冊です.

脊椎手術合併症回避のポイント
若手脊椎外科医が執刀する手術で起こりうる合併症に限定し,構成されている書籍である。起こる頻度の高い合併症,それらを起こしやすい場面(メルクマール:指標)を術式別に取り上げ,イラスト・写真とともに解説している。
各項目は,「なぜ起こるのか」「起こさないために」「起きてしまったら」「オペ時のメルクマール」の見出し4つで構成されている。「オペ時のメルクマール」では最初に[起こしやすい場面:注意するポイント/回避のポイント]を青文字で強調しているので,例:[移植骨の設置時:母床椎体の骨性終板は温存する](移植骨設置位置の不良 より),この部分を見ていくだけでも,その手術で注意しなければいけない合併症の回避ポイントが理解できる。
術式別の合併症情報が一目瞭然になっている本書を,執刀前に是非必見していただきたい。

≪US Labシリーズ7≫
用語・現象の原理を知って、検査にいかす!
腹部超音波検査の へぇ~!! これそうなんだ!
【検査中の用語や現象の疑問を解決!】「この用語の意味は?」「何でこの部分は見えないのだろう?」など一通り検査ができるようになってくると生じてくる「用語」や「現象」の疑問について解説する。用語・現象の意味や理由(根拠)を知ることで、一段上の検査や報告ができるようになる。
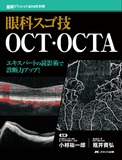
≪眼科グラフィック2019年別冊≫
眼科スゴ技 OCT・OCTA
エキスパートの読影術で診断力アップ!
【まぎらわしい症例に挑戦! 診断クイズ付き】大きく美しい症例写真を数多く掲載。OCT・OCTAの基礎から応用、一線で活躍する眼科医の読影術まで、すべてが身につく一冊。まぎらわしい症例を見分けるチャレンジ問題、前眼部・後極部OCT、OCTAのアトラスも掲載。
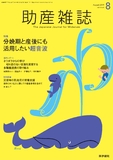
助産雑誌 Vol.73 No.8
2019年08月発行
特集 分娩期と産後にも活用したい超音波
特集 分娩期と産後にも活用したい超音波 妊娠中,健診で胎児の様子を確認したり,コミュニケーションツールとしても超音波を使用している助産師さんは多くいらっしゃると思います。本特集では,主に「分娩中」と「産後」の超音波の役立て方に注目します。例えば分娩中は胎児心拍や胎児の下降をみたり,胎盤早期剥離,回旋異常をみたりすることもできます。また産後は膀胱の残尿量のチェックや,恥骨直腸筋の評価も可能です。助産師が臨床現場で,今以上に超音波を活用できるヒントをご紹介します。
