
公衆衛生 Vol.83 No.8
2019年08月発行
特集 新型たばこ 健康影響と規制のあり方
特集 新型たばこ 健康影響と規制のあり方 -

臨牀透析 Vol.35 No.8
2019年7月号
既存のガイドラインを透析患者にどう活用するか
既存のガイドラインを透析患者にどう活用するか
CKD・透析患者では既存のGL をどのように読み替えるべきか,注意すべき点は何かなどを…それらの疾患や病態に精通した諸先生に記載していただいた.

臨牀消化器内科 Vol.34 No.9
2019年8月号
大腸ポリープ取り扱いのUp to Date
大腸ポリープ取り扱いのUp to Date
大腸ポリープの診断,治療はこの20 年足らずで目覚ましい発展をみせている.ポリープの切除方法については施行医や医療機関による違いも多いと思われる.重要なのは安全かつ確実に病変を切除することであり,それぞれの切除方法の特徴,すなわちメリット,デメリットをきちんと把握したうえで適切に選択することである.そして何より,治療前の正確な内視鏡診断が基本となることはいうまでもない.

INTESTINE Vol.23 No.4
2019年7・8月号
原因不明消化管出血(OGIB)
原因不明消化管出血(OGIB)
OGIB の原因疾患は小腸疾患とほぼ同義語と考えてよいと思われ,その診断・治療のたのdevice が21世紀初頭に登場したカプセル内視鏡,バルーン内視鏡であり,ほぼ20 年が経過したことになる.

現場で使える臨床研究法
2018年4月施行の「臨床研究法」について,法の対象の解釈,医療機器研究に及ぼす影響,企業との研究資金提供を巡る契約や利益相反管理のポイント,認定臨床研究審査委員会の運営,jRCTへの対応,罰則規定の詳細など,現場の研究者の立場に立って,具体的に何をどうすればよいのか,実務上のポイントをわかりやすく解説した.
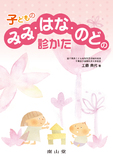
子どものみみ・はな・のどの診かた
症状を自ら訴えることもできない,診るにもひと手間かかるのが小児,特に乳幼児の診療である.小児耳鼻咽喉科の専門医が上手に小児を診るポイントから,治療のコツや家族へのアドバイスまで,豊富なチャート図や症例写真とともに,見開き2ページでわかりやすく解説した一冊.

漢方治療のファーストステップ 第2版
漢方薬の基本的な使用法のすべてがマスターできる実用書.臨床に直結する内容をわかりやすく読者に提供するために,箇条書きと表を多用し簡潔な表現とした.漢方用語の使用は必要最小限にして,使用頻度が高く使える処方を中心に,また,疾患・症候は漢方治療の有用なものに限定して解説.ベテラン医師の診療ノウハウが満載の頼れる一冊.

心血管内分泌検査から読み解く 降圧薬 俺流処方
これまで画一的に取り扱われてきた本態性高血圧の治療を心血管系内分泌系の臨床検査値などにより病態に応じてグループ分けし,高血圧治療のエキスパートがJSH2009から一歩踏み込み,臨床経験上妥当と考え実践で選択している降圧薬の「俺流」処方をそれぞれの専門分野の立場から,エビデンスならびに自身の考え方を含めて解説.

実験医学 Vol.37 No.13
2019年8月号
【特集】最も修復しにくい臓器 中枢神経を再生せよ!
【特集】最も修復しにくい臓器 中枢神経を再生せよ! 困難とされてきた脊髄損傷や脳卒中による中枢神経障害の治療法として,近年,細胞治療や抗体医薬の開発が進みつつあります.分子メカニズムの解明から治療法確立に挑む研究最前線.今年の科研費最新情報も必見.

パッと出してすぐわかる
胆・膵 超音波アトラス
検査する場所を選ばず機器も簡便で非侵襲的であることから,超音波検査の有用性が改めて見直されており,臨床に不可欠となっている。しかし,正確な画像を描出し,診断に役立てることは実際には難しく,臨床でできるだけ多くの画像をとり,読む経験を積むことが重要とされる。
本書では,臨床でよく出会う疾患から,まれな疾患まで,造影エコーを含む豊富な画像とともに取り上げている。また,「画像を見てシェーマが描ける」ことを目標に,どこに何が描出されているのか,疾患の概要と併せて,わかりやすいシェーマで易しく解説。必要に応じて,CT/MRI,病理画像も併載。本書を通読すれば,自信を持って腹部エコーの撮像・読影ができるようになる。
「肝脾」「胆膵」の二部構成で,あなたはもう腹部エコーのエキスパート!

パッと出してすぐわかる
肝・脾 超音波アトラス
検査する場所を選ばず,機器も簡便で,非侵襲的であることから,超音波検査の有用性が改めて見直されており,臨床に不可欠となっている。しかし,正確な画像を描出し,診断に役立てることは実際には難しく,臨床でできるだけ多くの画像をとり,読む経験を積むことが重要とされる。
本書では,臨床でよく出会う疾患から,まれな疾患まで100超の疾患を取り上げた。典型例だけでなく,判断が難しい症例まで網羅。また,「画像を見てシェーマが描ける」ことを目標に,どこに何が描出されているのか,疾患の概要と併せて,わかりやすいシェーマで易しく解説。必要に応じて,CT/MRI,病理画像も併載。本書を通読すれば,自信を持って腹部エコーの撮像・読影ができるようになる。
「肝脾」「胆膵」の二部構成で,あなたはもう腹部エコーのエキスパート!

臨床医のための 医学からみた認知症診療 医療からみる認知症診療―診断編
認知症診療において,ガイドラインや医学研究などの医学的な知識と実臨床で実際に役立つ技術の双方を学ぶ必要があるなか,
実際には双方間にギャップが存在するのが現状である.そこで本書では,双方の立場からディベート形式で認知症の診断について平易に解説した.
認知症の診断スキル向上に役立つ1冊である.

臨床で役立つ基本知識から評価・訓練まで
すぐに使える!実践リハビリ技術マスターガイド 第2版
財団法人竹田綜合病院において実際に行われている新人リハビリテーションスタッフ向け教育プログラムを書籍化した初版は
各所で高い評価を得ているが、本書はその内容を更にブラッシュアップし、また現状に即して適宜アップデートを行った改訂第2版である。
OT・PTの新人スタッフや学生の学習に最適の一冊.

美容皮膚科ガイドブック 第2版
皮膚のことをもっと知りたいけど、難しい話はイヤ。……そんな人におススメします!
皮膚の美容に興味を持つ初学者に向けて,美容皮膚科診療に必要な基本的知識を分かりやすく解説した入門書.
美容皮膚の心構えからスキンケアについて,患者のニーズが高いシミ・シワ・たるみなどの具体的な治療方法までをまとめた.
各領域を現在活躍中のエキスパートが丁寧に分かりやすく解説し,医師のみならず美容関係者にとっても理解しやすい内容となっている.
美容皮膚に関わる全ての人にお勧めしたい1冊.

がん看護 Vol.24 No.6
2019年7-8月
服薬アドヒアランスを高める看護
服薬アドヒアランスを高める看護 がんの医学・医療的知識から経過別看護、症状別看護、検査・治療・処置別看護、さらにはサイコオンコロジーにいたるまで、臨床に役立つさまざまなテーマをわかりやすく解説し、最新の知見を提供。施設内看護から訪問・在宅・地域看護まで、看護の場と領域に特有な問題をとりあげ、検討・解説。告知、インフォームド・コンセント、生命倫理、グリーフワークといった、患者・家族をとりまく今日の諸課題についても積極的にアプローチし、問題の深化をはかるべく、意見交流の場としての役割も果たす。

漢方薬で癒すこころとカラダ
Dr.イケノの思春期お悩み相談室
思春期特有のストレスに起因する不定愁訴や学校行事が原因の症状に対し、東洋医学的視点から症状緩和をはかる治療法を紹介。こういった症状で、こんな状況のこの子には○○の処方、というように、多数症例をあげ処方までの流れをわかりやすく解説しています。医療関係者だけでなく、患者さんご本人やご家族、学校関係者など、広く読んでいただきたい思春期漢方の入門書。

高次脳機能障害豆ブック
失語、失認、失行など高次脳機能障害を診る際の要点をわかりやすくまとめた1冊。訓練・介
入へとつながるポイントはコラムでも紹介。臨床の場で、実習場面で、さっと確認ができるポケット版!

INTENSIVIST Vol.11 No.3 2019
2019年3号
特集:栄養療法アップデート 後編
特集:栄養療法アップデート 後編

LiSA Vol.26 No.7 2019
2019年7月号
徹底分析シリーズ:麻酔科からの「お・も・て・な・し」 ラグビーワールドカップ,そしてTOKYO2020/症例カンファレンス:複数回の全身麻酔既往のある肥満小児の下腿ボトックスⓇ 注入療法/異国交流インタビューin English:鎮静の安全性を高めるために Dr. Charles Cotéに聞く①
徹底分析シリーズ:麻酔科からの「お・も・て・な・し」 ラグビーワールドカップ,そしてTOKYO2020/症例カンファレンス:複数回の全身麻酔既往のある肥満小児の下腿ボトックスⓇ 注入療法/異国交流インタビューin English:鎮静の安全性を高めるために Dr. Charles Cotéに聞く①

画像所見のよみ方と鑑別診断 第2版
胆・膵
画像に認められた所見から何を読み取り、何を考えるべきか―診断に至る道筋が見えるアトラス。好評を博した初版のコンセプトを継承しつつ大改訂を敢行。1症例の画像・病理像を見開き2ページに収め、エキスパートの着眼点、思考の流れを追うことができるユニークな構成。画像所見と病理像の対比により鑑別診断のポイントが理解できる。胆膵領域の画像診断の奥深さが感じられる184症例を収載。
