
月刊/保険診療 2015年7月号
特集/レセプトの“大学” ~2015年夏季講座「傷病名の全知識」~
特集/レセプトの“大学” ~2015年夏季講座「傷病名の全知識」~
1時限目 「傷病名」にはいろいろな分類がある
2時限目 「傷病名」の構造・言葉の意味を知る
3時限目 レセプトの「適応疾患」を極める/佐藤達哉
4時限目 「DPC病名」を極める/阿南誠,福島祥子
日本の元気な病院&クリニック/江戸川病院
定年後の継続雇用に長年の実績 新卒採用も開始し質的向上を図る
視点健康づくり無関心層の行動変容をもたらす新しいアプローチ―「健康ポイント」/久野譜也

月刊/保険診療 2015年8月号
特集/医療の現場から“地域包括ケア”を考える~患者を家に帰せばよいのか~
特集/医療の現場から“地域包括ケア”を考える~患者を家に帰せばよいのか~
Part1 “地域包括ケア”の現場から
1 急性期から在宅までの機能を法人内で担う/牧田総合病院本院
2 “最期の場”がある地域をつくる/ホームオン・クリニック
3 在宅生活を支える交互利用の促進/ウェルケア新吉田
4 要介護者の重度化による介護現場の負担増/川田英治
5 地域包括ケアのゴールは,“看取り”/本間郁子
6 地域全体の連携の潤滑油としての役割を果たす/澤登久雄
7 点数が付かない現場負担の増加/堀田智恵子
Part2 【鼎談】“地域包括ケア”というプランと現実の狭間/芝田英昭,宮島俊彦,宮武剛
Part3 患者を家に帰せばいいのか
●克服すべき課題はあるが,地域包括ケアは前向きに取り組むべき/杉山孝博
●システムありきではない地域の人のためのケア/山岡淳一郎
新連載 人材を活用する“5つのチカラ”第1回 みるチカラ/下田静香
日本の元気な病院&クリニック/玉川病院
ラダーシステムとポートフォリオで看護職の能力と「質」の向上を図る
視点「ヘルスケア・カイゼン」が医療機関を変える/浅野信久
第42回診療報酬請求事務能力認定試験〔医科〕:問題と解説

月刊/保険診療 2015年9月号
特集/“患者目線”からの院内改革~医療機関マーケティングの基本フォーム~
特集/“患者目線”からの院内改革~医療機関マーケティングの基本フォーム~
Part1 なし崩し的な規制緩和の流れに抗し,財源論に縛られない議論を
外科系学会社会保険委員会連合(外保連)会長/岩中督
Part2 空床活用で,医療が必要ない人のための施設
「スキルドナーシングウォード」を
一般社団法人日本慢性期医療協会会長,医療法人平成博愛会理事長/武久洋三
特集 “患者目線”からの院内改革~医療機関マーケティングの基本フォーム~
Part1【座談会】“患者目線”からの発想転換/岩本ゆり,野尻一之,村尾孝子,伊藤雅教
Part2“患者目線”で医療機関を変えた!
1 満足度調査を踏まえたモニター会議で“患者目線”を活かす/川崎市立井田病院
2 患者の声を起点に進化する山下病院の取組み/加藤良平
Part3“患者目線”こそが医療機関マーケティングの基本だ!/志賀嘉典
Part4“患者目線”からの院内改革ポイント50
連載特集 2016年診療報酬改定を読み解く1

月刊/保険診療 2015年10月号
特集/薬剤・材料の完全マネジメント術~“モノ”の購入・管理・請求を極める~
特集/薬剤・材料の完全マネジメント術~“モノ”の購入・管理・請求を極める~
Part1 薬剤・材料のまるごと全知識/監修:【薬剤】佐々木忠徳,【材料】柴崎敦
1 薬剤・材料の基礎知識
2 薬剤・材料マネジメント入門
Part2 【座談会】薬剤,材料のマネジメントを極める/内田力,田中聖人,古木壽幸,笠原庸介
Part3 薬剤・材料──12の最適マネジメント術/宮本健
Part4 薬剤・材料の請求ミス事例ポイント20/長面川さより
新連載 “保険診療”の教室【元審査委員による特別講義】 【第1回】国民皆保険制度は医療者のためになっているか?/進藤勝久
日本の元気な病院&クリニック /西台クリニック画像診断センター
「日本流」の検診をアピールし,メディカルインバウンドを惹きつける
連載特集 2016年診療報酬改定を読み解く2
Part1 内科診療プロセスの評価を実現する内科系学会社会保険連合(内保連)代表/工藤翔二
Part2 今後の診療報酬改定は“費用対効果”が評価軸となる中央社会保険医療協議会公益委員,一橋大学大学院商学研究科教授/荒井耕

月刊/保険診療 2015年11月号
特集/完全保存版 職場のルールBOOK~病院・クリニック編~
特集/完全保存版 職場のルールBOOK~病院・クリニック編~
Part1 7対1は患者病態像に合わせた評価へ
中医協・入院医療等の調査・評価分科会会長/武藤正樹
Part2 DPC暫定調整係数廃止のソフトランディングを図る
中医協・DPC評価分科会会長/小山信彌
特集 完全保存版 職場のルールBOOK~病院・クリニック編~
Part1 【座談会】「職場のルールBOOK」作成委員会/鷹取敏昭,寺松輝彦,正木義博,鈴木紀之
Part2 「職場のルール違反」ケーススタディ20/岡本真なみ,福間みゆき
Part3 「職場のルールBOOK」全140カ条
日本の元気な病院&クリニック /北里大学病院
「新病院プロジェクト」が完了,「成長する病院」に生まれ変わる
視点第二期安倍政権の医療制度改革/二木立
連載特集 2016年診療報酬改定を読み解く3

月刊/保険診療 2015年12月号
特集/地方包括ケア時代の「在宅医療」最適マネジメント術/監修:全国在宅療養支援診療所連絡会
特集/地方包括ケア時代の「在宅医療」最適マネジメント術/監修:全国在宅療養支援診療所連絡会
特集Ⅰ 地方包括ケア時代の「在宅医療」最適マネジメント術/監修:全国在宅療養支援診療所連絡会
Part 1 在宅医療マネジメントの最前線
1 都市部の地域密着型病院として,患者ニーズに合わせた在宅の取組みを強化/日扇会第一病院
2 失われた“縁”を地域包括ケアで再構築する/新田クリニック
Part 2 【座談会】在宅医療マネジメントを成功させる12の秘訣/苛原実,田村豊,中村哲生,村上典由
Part 3 在宅医療の最適マネジメント術/荒井康之,太田秀樹,北澤彰浩,長縄伸幸,英裕雄,和田忠志
特集Ⅱ 最新時事NEWS総まとめ2015
日本の元気な病院&クリニック /偕行会城西病院
赤字自治体病院を継承し,強い信念で再建を果たす
視点 医師事務作業補助者の業務実態とハイスキル人材の位置づけ/瀬戸僚馬
連載特集 2016年診療報酬改定を読み解く4
●機能の分化と強化が,着々と進められていく
中央社会保険医療協議会診療側委員/万代恭嗣

≪シリーズ生命倫理学 6≫
生殖医療
生殖医療は他分野とは比べものにならないくらい急速に展開してきた、そして今も発展しつつある領域である。そのため、医学・医療の進捗に対し、生命倫理をはじめとする社会的評価が後追いしている状況にある。本書は、生殖医学ならびに倫理学の個々の領域のリーダーである著者たちが、その最前線の現場、研究内容をアップ・ツー・-デイトに解説し、「倫理に基づく医学」か、それとも「医学に基づく倫理」かとの問いを突きつけることにより、今後の生殖医療の在り方を考えた。

≪シリーズ生命倫理学 5≫
安楽死・尊厳死
哲学的な視点から、またキリスト教、仏教の視点から生命を考える総説的考察に続いて、日本をはじめ、欧米と近隣国の安楽死と尊厳死をめぐる各国の事情、運動、判決事例、法律案を紹介、日本のガイドラインを詳述する。 本巻は、安楽死論の要となる「個人の自由の尊重」と「安楽死合法化が社会にもたらす望ましくない影響の排除」という二つの価値のせめぎあいについて、またキリスト教の視点から、患者と彼を支える者との関係性に重点を置いた安楽死に対する考察、またホスピス活動を仏教のあゆみに重ねる視点からの論考など、安楽死・尊厳死をめぐる課題を総説的に示す一方、欧米・近隣国の安楽死・尊厳死をめぐる事情や、日本の尊厳死容認運動と終末期の延命措置中止に関する法律案の紹介、さらに安楽死は処罰されるべきかの議論を、安楽死事例判決を読み解きながら考察する。 安楽死・尊厳死を考えるうえで大切な視点として、患者や患者を支える家族に対する適正な生命倫理、医療倫理を踏まえた対応を医療界に提示している。日本生命倫理会の問題状況を医療の現場から描くとともに、「救急医療における終末期医療に関する提言(ガイドライン)」を詳述して「人工延命治療の差控えと中止の過剰なまでの区別による弊害」から生じる机上の空論からの脱却を示唆する。

健康行動理論による研究と実践
「健康日本21(第二次)」で取り上げられている生活習慣・社会環境の改善の研究・実践に活用できる、健康教育・ヘルスプロモーションの理論・モデルを、日本国内の事例とともにコンパクトに紹介する。さまざまな理論が、個人内、個人間、集団レベルに分けて歴史的な変遷をもとにわかりやすく整理されている、初学者や実務者必携のハンドブック。
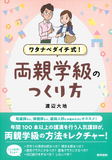
ワタナベダイチ式! 両親学級のつくり方
両親学級を運営するのに必要な考え方、スキル、コツと、さまざまな施設での両親学級の取り組みを紹介。第1部では、両親学級で伝えるべき内容・集客の仕方・プログラムの組み方など、いかに満足度の高い学級を開催するかという知識をまとめ、第2部では全国の病院や助産院などに渡辺氏が赴き、両親学級の企画から実際の様子、学級のポイントをまとめている。「助産雑誌」で人気の連載が1冊に!

≪シリーズ生命倫理学 4≫
終末期医療
終末期医療の臨床における狭い意味での医療倫理問題だけでなく、死の教育や医療者教育、日本人のスピリチュアリティなど、今後のあるべき終末期医療を考える上で重要な人間の死や死生観をめぐる文化・社会的課題についても広く考察し、終末期医療をめぐる既存の概念や理論を批判的に問い直す。 現場で役立つ具体的な事例を盛り込みながら、基本事項や概念から最先端の話題までこのテーマに興味を持つ人なら誰でも理解できるよう平易に解説。

月刊/保険診療 2016年1月号
特集/「NO」と言えない医療制度改革~TPPと国民皆保険の憂鬱な未来~
特集/「NO」と言えない医療制度改革~TPPと国民皆保険の憂鬱な未来~
Part 1 【座談会】社会保障とTPP──そして誰も 「NO」と言えなくなる/植草一秀,金子勝,小池晃,本田宏
Part 2 医療界はなぜ「NO」と言えなくなってしまったのか
1 なぜ社会保障費抑制・規制改革に歯止めがかからないのか/岡田知弘
2 医療保険制度,混合診療のあり方について国民的な議論を!/上昌広
3 国民の医療制度に対する理解を高め,アメリカの圧力に屈服しない政権を/東谷暁
Part 3 21世紀「医療制度改革」総まとめ
新連載 医療事務・実践深考塾~医学管理・在宅医療編~/下田野仙人
日本の元気な病院&クリニック /小山記念病院
「FIVE HEART Card」の活用でホスピタリティの向上を図る
視点 在宅医療の現場から/山岡淳一郎
第43回診療報酬請求事務能力認定試験(医科):問題と解説
連載特集 2016年診療報酬改定を読み解く5
●2025年のあるべき姿を目指し,前回を踏襲した議論が続く
社会保障審議会医療保険部会 部会長/遠藤久夫

月刊/保険診療 2016年2月号
特集/2016年診療報酬改定はこうなる!~「主要改定項目・新旧対照表」完全収載~
特集/2016年診療報酬改定はこうなる!~「主要改定項目・新旧対照表」完全収載~
特集Ⅰ 2016年診療報酬改定はこうなる!~「主要改定項目・新旧対照表」完全収載~
個別改定項目について/中医協答申
/2016年1月27日,2月10日中央社会保険医療協議会・総会
工藤高
特集Ⅱ 診療DATA完全解読術~カルテ・指示箋等の情報を読み解く~
Part 1 臨床事例&診療データ総まとめ
●内科の診療データ 「危機感をもたない患者(糖尿病)」
●外科の診療データ「駄菓子屋が閉まる日(直腸癌)」
/伊藤陽子,鹿島健,石井仁
Part 2 【座談会】診療データの統括・連係・活用術
/内田智久,中山和則,並木洋,橋本敦
Part 3 診療データ解読―60の着眼点
/秋岡美登惠,秋山貴志,阿南誠,小笠原一志,佐藤達哉,武田弘
●内科編
●外科編
連載特集 2016年診療報酬改定を読み解く6
●地域医療構想と診療報酬改定の両輪で,あるべき医療提供体制の構築を目指す
中央社会保険医療協議会支払側委員/幸野庄司

月刊/保険診療 2016年6月号
特集/2016年診療報酬改定の読解術〔Ⅰ〕~2016年改定への作戦会議~
特集/2016年診療報酬改定の読解術〔Ⅰ〕~2016年改定への作戦会議~
Part 1 2016年改定への戦略と対策〔上〕
1 地域でどの機能を選択するか明確化する必要がある/猪口正孝
2 地域包括ケア病棟は地域医療構想の要となる/仲井培雄
3 リハビリテーションの成果がきびしく問われる時代が続く/石川誠
Part 2 【座談会】2016年改定への作戦会議
/甲斐尚仁,中村哲生,橋本敦,工藤高
Part 3 2016年診療報酬改定対策──6枚の企画書〔上〕
/小松大介(1 2),酒井麻由美(3)
1 7対1入院基本料改定への対応
2 回復期リハビリテーション病棟改定への対応
3 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料のマイナスへの対応策
別冊 Part 4 新点数Q&A総まとめ
日本の元気な病院&クリニック /国立成育医療研究センター
「次の世代へつなげる医療」を──短期滞在施設「もみじの家」オープン
連載特集 2016年診療報酬改定を読み解く8
●地域包括ケアのなかで重要なかかりつけ医機能──今後さらに発展させる方策を
中央社会保険医療協議会診療側委員/松本純一

月刊/保険診療 2016年7月号
特集/2016年診療報酬改定の読解術〔Ⅱ〕~新点数による算定・請求実例集~
特集/2016年診療報酬改定の読解術〔Ⅱ〕~新点数による算定・請求実例集~
Part 1 2016年改定への戦略と対策〔下〕
1 2016年度改定への戦略と対策─在宅医療/北澤彰浩
2 2016年度改定への戦略と対策─精神科病院の視点から/馬屋原健
3 慢性期医療は在宅までの医療・看護・介護に広くかかわるべき/富家隆樹
Part 2 2016年診療報酬改定対策――6枚の企画書〔下〕/小松大介(1),酒井麻由美(2 3)
1 障害者病棟+療養病棟改定への対応
2 地域移行機能強化病棟への転換による病床削減
3 加算算定の効果アップ~医師事務作業補助体制加算の事例~
Part 3 新点数による算定・請求実例集
/栗林令子,長面川さより,水谷公治,宮本健,出口理恵
日本の元気な病院&クリニック/済生会熊本病院
アライアンス病院を巻き込んだ「転帰報告事業」の取組み

月刊/保険診療 2016年8月号
特集/進化する医療機関アメニティ~「カイゼン」プロジェクト会議~
特集/進化する医療機関アメニティ~「カイゼン」プロジェクト会議~
Part 1 アメニティ改善プロジェクト会議
/中山和則,松本忠男,吉田ともこ,鈴木将史
Part 2 アメニティ改善の成功事例に学ぶ
Part 3 アメニティ&環境衛生――プロフェッショナルの視点
患者満足度,スタッフ満足度の向上を意識したアメニティ改善/澤匡文
環境衛生の“カイゼン”で,時間・労力・コストをスリム化/松本忠男
日本の元気な病院&クリニック/東京衛生病院
ボランティアスタッフが「チームの一員」として院内で活動
視点「医薬分業」をめぐる現状と今後の課題/川渕孝一
第44回診療報酬請求事務能力認定試験(医科):問題と解説

月刊/保険診療 2016年9月号
特集/医療機能選択の戦略 to 2025~地域医療構想と自院のポジショニング~
特集/医療機能選択の戦略 to 2025~地域医療構想と自院のポジショニング~
Part 1 【鼎談】「地域医療構想」を問う
/芝田英昭,松田晋哉,村上正泰
Part 2 【誌上経営企画会議】「医療機関の選択」を問う
「急性期」の選択を問う/並木洋,松谷厚聖,工藤高
●高度急性期,急性期病院の戦略/工藤高
「回復期・慢性期」の選択を問う/田村大輔,皆川博行,小松大介
●回復期と慢性期における戦略/小松大介
「在宅医療」の選択を問う/苛原実,英裕雄,大石佳能子
●地域包括ケアシステムの要となる在宅医療の経営戦略/大石佳能子
日本の元気な病院&クリニック/相澤東病院
地域包括ケアの要として,近隣の高齢者をきめ細かく支援する
視点 マイナンバーで医療はどう変わるか1「マイナンバーと医療のICT化の行方」/金子麻衣

月刊/保険診療 2016年10月号
特集/「事務部門」発の医療機関改革!~事務部門主導の企画・立案事例集~
特集/「事務部門」発の医療機関改革!~事務部門主導の企画・立案事例集~
Part 1 「事務部門」が医療機関を変える!
一人ひとりが経営者としての自覚をもち,主体的に活動する
/東埼玉総合病院
患者だけでなく職員,地域を大切にする取組みが病院を変える
/昭南病院
Part 2 「事務部門」主導の企画・立案22事例
Part3 「事務部門」の未来―この10人に聞く
/正木義博,久保田巧,齋藤哲哉,植松美知男,中島雄一,中林梓,石井富美,青木忠祐,在原右,肥田守
日本の元気な病院&クリニック原宿リハビリテーション病院
歩行補助ロボット導入に込められたこれからのリハビリ病院のあり方
視点マイナンバーで医療はどう変わるか2「医療のICT化と個人情報保護の視点」/宮下紘

月刊/保険診療 2016年11月号
特集/レセプトの“大学”―2016年秋期講座~レセプトのための医学・臨床の実践知識~
特集/レセプトの“大学”―2016年秋期講座~レセプトのための医学・臨床の実践知識~
1時限目 【鼎談】レセプトの「なぜ?」を探求する
/坂井田晃,佐藤達哉,長面川さより
2時限目 12疾患=12レセプトを医学・臨床面から総点検する
/【事例解説】秋山貴志,大下裕矢,小笠原一志,佐藤達哉,長面川さより
日本の元気な病院&クリニック /姫野病院
食事の改善と“医療と介護の融合”で,「寝たきり」をつくらない
視点 医療での活用が期待される“ウェアラブル・ヘルスケア”/浅野信久

月刊/保険診療 2016年12月号
特集/「個別指導」チェックポイント750~全国6厚生局「指摘事項」傾向と対策
特集/「個別指導」チェックポイント750~全国6厚生局「指摘事項」傾向と対策
Part1 【誌上対策会議】個別指導はこう乗り切る!/小林洋一,竹田和行,中山和則,浜野博
Part2 「個別指導」総まとめ
Part3 全国6厚生局――「指摘事項」全750/【ポイント解説】佐藤達哉,鈴木達也,武田匡宏,持丸幸一
特集Ⅱ 最新時事NEWS総まとめ2016
日本の元気な病院&クリニック/藤枝市立総合病院
民間出身者の登用と若手プロジェクトで再起を図る
視点 新専門医制度の何が問題なのか1:新専門医制度を再考する/池田康夫
