
月刊/保険診療 2017年3月号
特集 保険外診療のリアリズム~拡大する「保険外」と「自費」の最適活用法~
特集 保険外診療のリアリズム~拡大する「保険外」と「自費」の最適活用法~
Part 1 「保険診療」&「保険外診療」総まとめ
Part 2 【座談会】「保険外診療」との上手なつき合い方/新井良和,佐々木英也,原茂順一,小松大介
Part 3 「保険外診療」はどこまで拡大するか/藤原康弘,小川和宏,伊藤たてお
日本の元気な病院&クリニック /maggie’s tokyo
イギリス生まれの“がんケアリング”自分を取り戻すためのサポートを提供
視点医薬品・医療機器の市場と価格はどうなるか/橋爪章

月刊/保険診療 2017年4月号
特集 レセプトの大学─2017年春期講座~請求もれを限りなくゼロに近づける240の視点~
特集 レセプトの大学─2017年春期講座~請求もれを限りなくゼロに近づける240の視点~
1時限目 【鼎談】「請求もれ・過少請求」のメカニズムを解き明かす/坂井田晃,瀬川研一,中林梓
2時限目 「請求もれ・過少請求」を探せ!/大下裕矢,酒井麻由美,佐藤達哉,長面川さより
3時限目 「請求もれ・過少請求」総点検マニュアル─全240ポイント/小笠原一志
日本の元気な病院&クリニック /キャップスクリニック代官山T-SITE
年中無休の小児科クリニックでめざすは“家族サポート医療”
視点日本の社会保障─財源問題とこれからの発展の方向性/唐鎌直義

月刊/保険診療 2017年5月号
特集 12枚の医業経営企画書~Plan Do Check Actionの実際~
特集 12枚の医業経営企画書~Plan Do Check Actionの実際~
Part 1 座談会【誌上経営企画会議】経営戦略・企画をいかに構築するか/久保田巧,兵藤敏美,堀畑利治,大石佳能子
Part 2 12枚の医業経営企画書
/石井富美,伊藤哲雄,小前貴志,角谷慶,北里淳,笹真人,澤田優香,中島雄一,福間みゆき,行本百合子,湯原淳平
日本の元気な病院&クリニック/武蔵野総合クリニック
いかなる患者にも対応する「コンビニエンス・クリニック」
視点3.11と小児甲状腺がんの現実/松崎道幸

月刊/保険診療 2017年6月号
特集 地域連携コーディネート術~地域包括ケアと地域連携室の役割~
特集 地域連携コーディネート術~地域包括ケアと地域連携室の役割~
Part 1 “地域連携”の近未来地図
Part 2 “地域連携”の仕事場拝見!
1 患者ファーストの病診連携目指し,地域に根ざした黒子役に徹する/総合大雄会病院/大雄会第一病院/大雄会クリニック
2 単なる「受入れ窓口」から脱却し,経営に参画し得る「情報センター」を目指す/光仁会第一病院
Part 3 【座談会】“地域連携”をどうコーディネートするか/斎川克之,田中範彦,成塚健一,村上典由
Part 4 “地域連携”と“地域包括ケア”――10年後のかたち
1 地域包括ケアシステムの国際的位置付けと政策動向を踏まえた今後の方向性/筒井孝子
2 地域包括ケア政策の総括から共生社会へ/猪飼周平
日本の元気な病院&クリニック/朝日大学歯学部附属村上記念病院
病院による病院のための共同購入でコスト削減に挑む
視点「健康ゴールド免許」導入の前に知るべきこと/近藤克則

月刊/保険診療 2017年7月号
特集 医療&ビジネス――連携と交渉術~医産連携から医商連携“まちづくり”まで~
特集 医療&ビジネス――連携と交渉術~医産連携から医商連携“まちづくり”まで~
Part1 医療関連ビジネス図鑑
Part2 ビジネスの視点 22枚の医療関連ビジネス地図
Part3 医療機関の視点 【座談会】民間ビジネスとの連携と交渉のメソッド/中山和則,橋本敦,兵藤敏美,清水仁
Part4 地域の視点 医商連携による“まちづくり” ~“よって館ね”を中心とした医商連携「健軍商店街」の取組み~/健軍商店街・熊本市医師会(熊本県熊本市)
日本の元気な病院&クリニック/飯塚病院
「セル看護提供方式」の導入で“患者のそばにいる看護”を実現
視点薬価制度と費用対効果/五十嵐中

月刊/保険診療 2017年8月号
特集 医業収支改善の3つの戦略 1の巻
特集 医業収支改善の3つの戦略 1の巻
Part1 医業利益増&診療単価アップの方程式/小松大介
Part2 【座談会】いかに診療単価を上げるか/井上貴裕,鈴木学,正木義博,工藤高
Part3 【ケーススタディ】診療単価アップの“7メソッド” /内田亮太,森本陽介,世古口務,伊藤哲雄,根本欣司郎,鄭承容
日本の元気な病院&クリニック/公立甲賀病院組合/公立甲賀病院 「甲賀流三方よし」を踏まえたプロジェクトで地域本位の医療を目指す
視点トランプ政権と日本の社会保障への影響/萩原伸次郎
新連載 プロの先読み・深読み・裏読みの技術/工藤高
『地域医療構想を「脅威」とせず,情報入手の「機会」と捉える』
第46回診療報酬請求事務能力認定試験 (医科):問題と解説
“診療単価”アップを極める

月刊/保険診療 2017年9月号
特集 医業収支改善の3つの戦略 2の巻
特集 医業収支改善の3つの戦略 2の巻
Part1 “患者数アップ”の方程式/小松大介
Part2 “増患”のヒント総まとめ
Part3 【座談会】いかに患者増を図るか/佐々木英也,永井孝英,野沢剛,柴田雄一
Part4 【ケーススタディ】最適な患者増の “6メソッド” /上原繁夫,長田祐記,鈴木竹仁,原田宗記,松村眞吾
日本の元気な病院&クリニック/竹川病院
目指す理想像をビデオで具体化 職員の意欲と行動を喚起する
視点医療における快適職場形成に向けた取組み
~安心安全で,患者と医療者に,ともに優しい医療の構築に向けて~/浅野信久
連載特集 2018年診療報酬・介護報酬同時改定を読み解く1
●2025年を見据え地域医療構想を診療報酬で支える
厚生労働省医務技監/鈴木康裕
“増患”の法則

月刊/保険診療 2017年10月号
特集 医業収支改善の3つの戦略 3の巻
特集 医業収支改善の3つの戦略 3の巻
Part1 “コスト削減”の方程式/小松大介
Part2 【座談会】いかにコスト減を図るか/在原右,池上健二,番場省吾,伊藤雅教
Part3 【ケーススタディ】最適なコスト減の “6メソッド”/青木寿幸,太田衛,岡大徳,首藤崇,田中憲吾,松村眞吾
Part4 医業経営改善の3つの戦略──34の要諦
日本の元気な病院&クリニック/織田病院
退院後2週間をしっかり支えるメディカル・ベースキャンプ
連載特集 2018年診療報酬・介護報酬同時改定を読み解く2
●2025年だけでなく,その先の人口減少も見据えた長期的な展望が必要
中央社会保険医療協議会 診療側委員/松本純一
“コスト減”の全技術

月刊/保険診療 2017年11月号
特集 2018年同時改定で変わる
特集 2018年同時改定で変わる
Part1 2018年同時改定に向けた議論──現時点の総まとめ
Part2 医療と介護の “構造変化”の読み解き方
1 2018年同時改定から2025年に向かう医療と介護の“構造変化”/松田晋哉
2 医療と介護の構造変化(介護保険による医療の代替)と課題/伊藤周平
Part3 【対談】2018年同時改定で医療と介護はどう変わるか/工藤高,小松大介
Part4 【座談会】医療と介護の “灰色の境界線” /安仁屋衣子,内田美沙子,田村大輔,中村哲生,田中律子
日本の元気な病院&クリニック/東京曳舟病院
「断らない医療」 の実践で救急・災害病院としての地位を確立
連載特集 2018年診療報酬・介護報酬同時改定を読み解く3
●IT化による効率化努力が反映されることを期待
公益社団法人全日本病院協会会長,中央社会保険医療協議会・診療側委員/猪口雄二
医療&介護“境界線”の歩き方

月刊/保険診療 2017年12月号
特集 2018年同時改定に向けた 間違いだらけのデータ&シミュレーション
特集 2018年同時改定に向けた 間違いだらけのデータ&シミュレーション
Part1 医療関連データの現在形
【解説】小笠原一志,橋本大輔,皆川昇司
Part2 【対談】データ&シミュレーション取扱説明書/兵藤敏美,吉田克己
Part3 【ケーススタディ】間違いだらけのシミュレーション事例×7/大下裕矢,笹真人,新里雅則,渡辺優
特集Ⅱ 最新時事NEWS総まとめ2017
連載特集 2018年診療報酬・介護報酬同時改定を読み解く4
●増大する高齢者への「治し支える」医療を中心に据えた変革が必要
社会保障審議会・医療部会委員(日本病院会会長)/相澤孝夫

実験医学増刊 Vol.37 No.10
【特集】新時代が始まったアレルギー疾患研究
【特集】新時代が始まったアレルギー疾患研究 発症や重症化の機序が次々と明らかになり,それに基づく患者の層別化や分子標的薬の臨床応用が行われるなど,アレルギー疾患研究は近年新たな局面を迎えています.本書ではこのような病態解明・新規治療法開発の最前線を紹介します.

もっとよくわかる!炎症と疾患
あらゆる疾患の基盤病態から治療薬までを理解する
疾患を知るうえで避けては通れない【炎症】.関わる免疫細胞やサイトカインが多くて複雑ですが,「快刀乱麻を断つ」が如く炎症機序を整理しながら習得できます!疾患とのつながりについても知識を深められる一冊.
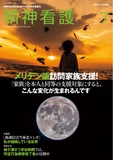
精神看護 Vol.22 No.4
2019年07月発行
特集 メリデン版訪問家族支援!「家族」を本人と同等の支援対象にすると、こんな変化が生まれるんです
特集 メリデン版訪問家族支援!「家族」を本人と同等の支援対象にすると、こんな変化が生まれるんです 「メリデン版訪問家族支援」という名前を聞いたことがあるでしょうか。これは、本人と家族とをまるごと支援する、英国発祥の技術です。日本ではこれまで、支援の対象者はあくまで本人で、家族は本人を支えるための資源の1つ、のように捉える傾向がありました。メリデン版訪問家族支援では、家族を利用者と同等の支援対象として位置づけ、一家にまるごとかかわっていきます。精神障害をもつ人が家庭内にいる場合、家族関係が家族全員にとっていいバランスで成り立っていることは少なく、誰かしらが、あるいは全員が我慢していると感じていることがよくあります。メリデン版訪問家族支援のアプローチにより、いつも「病気」を中心に生活してきた家族が、「健康的な暮らし」を望む家族へと変わり、家族の力が強まっていき、支援者も驚くような変化を見せていきます。この特集では、メリデン版訪問家族支援とはいったいどういうものなのか、そのメソッドを教えていただくとともに、ファミリーワーカーとなってケースにかかわった方たちの、個人的な経験や思いを教えていただきました。

看護管理 Vol.29 No.7
2019年07月発行
特集 病院データは“宝の山”! データ分析に基づく看護マネジメント 日々の数字を根拠に,現場を改革するために
特集 病院データは“宝の山”! データ分析に基づく看護マネジメント 日々の数字を根拠に,現場を改革するために 医療・看護サービスへのニーズの増大,それを支える人的パワーの減少,ひっ迫する国の財源状況など,病院を取り巻く環境は厳しさを増しています。病院看護部にも運営の効率化および生産性向上が迫られています。また,各地域の事情に応じた地域包括ケアシステムのさらなる最適化と住民の生活を守るための質保証も求められています。こうした中,将来を見通したマネジメントを適切に行うために,データや数値などの根拠に基づく議論や意思決定が必須です。現状を把握し,解決の方向性や目標を共有することで組織が一丸となった業務遂行が可能となるでしょう。本特集では,「重症度,医療・看護必要度」を中心に,病院データを分析するための基礎知識と,データに基づき病棟・看護部の改善につなげるための考え方について事例を通じて紹介します。データ分析に苦手意識を持つ読者にも,分かりやすく解説することを目指します。

看護研究 Vol.52 No.3
2019年06月発行
特集 Dr.Patricia A.Gradyを迎えて 看護研究者としての成長とキャリアパスを考える
特集 Dr.Patricia A.Gradyを迎えて 看護研究者としての成長とキャリアパスを考える -

看護教育 Vol.60 No.7
2019年07月発行
特集 あらためて協同学習を理解する
特集 あらためて協同学習を理解する 「ともに学んでいる仲間全体の意識を高めていくこと」を目的とした協同学習を看護教育に取り入れる試みは、めずらしくなくなりました。看護師には、医療現場でさまざまな人とともに協力して働くことが求められます。また、その教育において、従来からグループワークが多用されてきました。そのような理由から、協同学習と看護教育には親和性があったといえるでしょう。しかし、なかには、ジグソー法やラウンド・ロビンといった代表的な技法を活用しただけで、「教育に協同学習を取り入れた」としているケースも見受けられます。そこで今回、あらためて協同学習、協同教育とは何かをていねいに解説し、それを取り入れるための準備や実践として、研究会で広めているケースや大学、学校として取り組んでいるケースをご紹介します。「ともに学ぶ」ということを学生と教員の双方が意識できなければ、協同学習は機能しないということを忘れてはいけません。

理学療法ジャーナル Vol.53 No.7
2019年07月発行
特集 脳卒中患者の上肢に対する理学療法up to date
特集 脳卒中患者の上肢に対する理学療法up to date これまで脳卒中患者の上肢に対する理学療法は積極的に行われてきたとは言いがたいが,近年,運動学習理論の応用や神経科学の発展などによりいくつかの取り組みがなされている.本特集では,それらのなかからCI療法(constraint-induced movement therapy),促通反復療法,ボツリヌス療法を併用した理学療法,視覚誘導性自己運動錯覚療法,ロボティクスを導入した理学療法について取り上げた.すでにエビデンスレベルの高いものもあるが,緒に就いたばかりのものも含んでいる.これらをヒントに脳卒中患者の上肢に積極的に迫る理学療法士をめざしてほしい.

臨床皮膚科 Vol.73 No.7
2019年06月発行
-

病院 Vol.78 No.7
2019年07月発行
特集 多国籍社会に直面する病院
特集 多国籍社会に直面する病院 政府の外国人受け入れ強化に伴い,訪日外国人に加えて,在留外国人への医療提供も今後大きな課題となることが予想されている.本特集は,外国人医療対策を日本が国際化・多文化化する一つの契機と考え,「地域医療としての外国人医療整備」の先駆的な取り組みを紹介し,多国籍社会に備える一助となることを目指す.

病院 Vol.78 No.6
2019年06月発行
特集 地域の健康を支える病院
特集 地域の健康を支える病院 病院には,来院する患者に医療や保健サービスを提供するばかりでなく,地域住民や自院の職員に対しても健康的な生活が営めるようサポートする役割が求められている。また,病院職員が自らの健康づくりを通し,地域社会の健康を支える人材となれるよう行動することが望まれている。本特集では,地域社会に健康を発信する病院の先進的な取り組みを紹介し,今後,病院がより良質なサービスを地域で提供していくために必要な変革とは何かを考察する。
