
リンパ系局所解剖カラーアトラス
癌手術の解剖学的基盤
胃、膵臓、腹大動脈、胸管、卵巣・子宮、乳腺、舌・耳下腺など、身体の問題となる部位の動脈・静脈、神経系・筋膜などの位置関係と連絡形態について、精細なスケッチをカラーで示し、癌手術に資するよう意図したアトラス。

画像診断 Vol.40 No.11(2020年増刊号)
解剖と病態生理から迫る呼吸器画像診断
解剖と病態生理から迫る呼吸器画像診断 呼吸器(肺)の画像診断について,解剖にとことんこだわった病態生理の視点から,エキスパート達がわかりやすく解説!胸部単純X線写真・CTによるマクロ解剖と,TSCTによるサブマクロ解剖から構成.この1冊で正常解剖&鑑別診断がみえてくる.
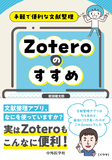
手軽で便利な文献整理 Zoteroのすすめ
速い,安い,簡単! のZoteroを使いこなそう!
Mendeley,Papers,ReadCube Papers,EndNote……文献管理アプリケーションには数多の選択肢が存在しますが,コスト,UI,環境,機能などその特徴は千差万別です.10年以上Zotero(ゾテロ)を愛用しているという岩田健太郎先生が「速い!」「安い(基本無料)!」「簡単!」というZoteroのアピールポイントを紹介しつつ,その導入法と使用法を易しくまとめました.
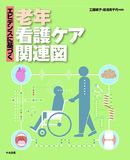
エビデンスに基づく老年看護ケア関連図
せん妄、熱中症、レビー小体型認知症、老衰、貧血、大腸がん、腸閉塞、COPD、誤嚥性肺炎、腎不全、大腿骨頸部骨折、白内障など、25疾患の病態生理・症状・治療・看護ケアについて解説。看護の目標と評価ポイントも示し、看護の振り返りにも活かせる視点を収載した。

BRAND NEW 心臓核医学
心臓核医学は機能画像診断法として臨床的有用性が確立され、さらに形態診断(CT/MR)との融合画像や分子イメ-ジングなど新しい展開を遂げつつある。「基礎」「症例」「展開」「エビデンス」「展望」の5部構成で、現時点での「心臓核医学のすべて」を網羅した内容となっている。心臓核医学に関わる循環器内科・外科医、放射線科・核医学科医および診療放射線技師の方々の座右の書として好適・必携の1冊。

ERの創傷
エビデンスと経験に基づくプラクティス
ERで最もありふれた手技が創処置である。にもかかわらずこれまでは各施設でそれぞれの流儀で行われてきているのが現状である。しかし、今日の医療技術の進歩と疾病構造の変化は従来の感染症への対策だけでなく、高齢ハイリスク患者への対応、除痛、回復時間、整容、機能、コスト面への配慮などより高度なものが求められてきている。また被覆材、縫合糸などもますます複雑多様化してきている。本書は経験とエビデンスに基づき創傷治癒の仕組みの原理、原則を根本から解説しながら、これらの進歩・変化に遅れない、最新の手技と方法を自在に駆使できるようイラストを中心に解説している。

心臓手術ビデオアトラス
手術手技と画像診断[Web動画付]
心臓手術の知識と手技について,高精細な手術動画と共に解説した.4Kビデオ顕微鏡システムによって撮影された動画は計400本以上,44時間超えの大ボリュームで,全てYouTubeで閲覧が可能.動画を観ることにより,エキスパートと同じ視野で手術のシミュレーションができる.また,症例解説では術前後の心エコー/CT画像も掲載,実際の手術所見との照合にも役立つ1冊.

バスキュラーアクセス実践ガイド
写真から学ぶ作り方と考え方

≪実験医学別冊≫
大規模データで困ったときに、まず図を描くことからはじめる生命科学データ解析
解析のゴールドスタンダードを学び、生成AIとの対話でPython・Rを使いこなす
シングルセル,メタゲノムseq,プロテオームなどの膨大なデータは『図』として可視化してこそ,真価が引き出されます.UMAP,MAプロット,ヒートマップ…本書では生成AIの力を借りながら自分で思いのままに可視化する方法を解説します!作図プロセスを通してデータの核心を掴み,より本質的な研究に進みたいあなたへ

バスキュラーアクセス サルベージ手術集
好評刊『バスキュラーアクセスの手技&Tips』の姉妹編が登場!
形成外科医と腎臓内科医がコラボレーションし, バスキュラーアクセス後のトラブルに対するサルベージ手術を, 部位毎に徹底解説!

小児科診療 Vol.88 No.9
2025年9月号
【特集】小児血管炎診療の基礎と臨床―IgA血管炎や川崎病だけではない多様な全身性疾患群―
【特集】小児血管炎診療の基礎と臨床―IgA血管炎や川崎病だけではない多様な全身性疾患群―
小児科領域では,川崎病やIgA血管炎(旧称:アレルギー性紫斑病,Henoch-Schonlein紫斑病)が比較的身近な存在ですが,実はそれだけではありません.学生時代にChepel Hill分類を学ばれた方も多いと思いますが,小児にも多様な血管炎が存在し,それぞれに応じた診療の工夫が求められます.
本特集は,小児血管炎に特化した非常に貴重な企画です.希少疾患であるがゆえに診療の機会が限られる一方で,遺伝子解析や生物学的製剤の導入,国際的な診療基準の整備など,めざましい進歩が続いています.だからこそ,まず「血管炎かもしれない」と疑い,気づくことが診療の第一歩です.
本特集が,小児血管炎にかかわる医師にとって実践的な知識と診療のヒントを提供する決定版(2025年度)となることを願っています.

看護学テキストNiCE
看護と研究 根拠に基づいた実践
Evidence-based Practice (EBP)
根拠に基づいた実践(EBP)のステップをわかりやすく解説.臨床の疑問からどのように文献を探し,研究結果を解釈・吟味して臨床の実践に適用するのかを,さまざまな研究デザインの実際の文献を通して例示.基礎的な統計知識や研究デザインの解説も収載.エビデンスを看護実践に活用するために必要なスキルを身に付けることができる1冊.

腰痛のプライマリ・ケア
腰痛者と向き合う時の必携書
腰痛は人類の8割以上が経験する症候である.本書では,整形外科外来はもちろん,総合診療科や一般内科外来において患者数の多い腰痛,すなわち障害程度が低いものの日常の診療で診る機会が多い腰痛を中心に解説する.腰痛のプライマリ・ケアで求められる“震源地(=病態)と震度(=障害程度)”の適切な評価方法と最適な対処方法について,運動器を専門としない臨床家が理解・実践できるよう,平易な表現で紹介する.
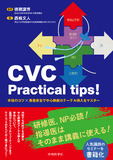
CVC Practical tips!
手技のコツ×患者安全で中心静脈カテーテル挿入をマスター
研修医,NP必読! 指導医はそのまま講義に使える! 人気講師のセミナーが待望の書籍化.「俺流」の技も良いですが,一番大事なのは「標準で安全で確実な」手技です.患者も医師も安全なCVCのテクニックが基礎からトラブルシューティングまで1冊で身につくこのテキストで,事故らないCVCをマスターしてself-esteemを高めよう!

≪みんなの呼吸器Respica2023年夏季増刊≫
人工呼吸器の換気モードと設定変更
【ホントに知りたい波形の動きだけ集めました】特に慎重な観察・判断を要する、人工呼吸器のモード変更や圧調整。「設定を触るとき」に着目し、換気モードの基礎から実践、波形から読み取るべき生理変化までビジュアルで徹底解説。さらに、一番知りたい変更前後のグラフィックを動画でチェック!リアルが学べる超決定版。
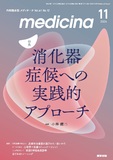
medicina Vol.61 No.12
2024年 11月号
特集 消化器症候への実践的アプローチ
特集 消化器症候への実践的アプローチ 内科診療に不可欠な情報をわかりやすくお届けする総合臨床誌。通常号では内科領域のさまざまなテーマを特集形式で取り上げるとともに、連載では注目のトピックスを掘り下げる。また、領域横断的なテーマの増刊号、増大号も発行。知識のアップデートと、技術のブラッシュアップに! (ISSN 0025-7699)
月刊、増刊号と増大号を含む年13冊

美容皮膚科ガイドブック 第3版
好評を博した美容皮膚の入門書.最先端の情報を踏まえて全面リニューアルした第3版.
美容皮膚の基本知識を平易に紹介した書の改訂第3版.初版刊行時から,皮膚科医だけではなく他科の医師や美容関係者からも好評を博した.前版から4年,美容皮膚の進歩は目覚ましく,さまざまな新しい薬剤,機器,治療方法が開発された.最新トピックスを盛り込むのはもちろん,今版では全ての項を見直し,全面リニューアル.各領域には現在活躍中のエキスパートを取り揃え,美容皮膚に関わる全ての人にお薦めしたいバイブルだ.

ICU看護クイックノート
・時間に追われることが多いICU(集中治療室)ナースが、頭に入れておきたい、本当に大事なことをコンパクトにまとめました。
・多岐にわたる診療科の重篤な患者さんをケアする、新人からベテランまで、幅広いナースに役立ちます。
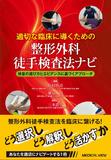
適切な臨床に導くための
整形外科徒手検査法ナビ
検査の選び方とエビデンスに基づくアプローチ
整形外科徒手検査法の結果を踏まえてどのような治療を施すべきか, 臨床思考に基づく治療の組み立て方について症例ベースで解説。各症例に対してなぜその検査法を選択したか, また選択しなかったのかを示すほか, 整形外科徒手検査法を選択する過程, 治療法選択の根拠となるエビデンス, 実際の治療が豊富な写真やイラストを用いてビジュアルに理解できる。
具体的な検査法の手順を詳説している姉妹書『適切な判断を導くための整形外科徒手検査法』と合わせて学習することで, 整形外科徒手検査法を自由に使いこなすことができるようになる。

レジデント必読
病棟でのせん妄・不眠・うつ病・もの忘れに対処する
精神科の薬もわかる!
・病棟で起こる精神科トラブルに対処できるようになりたい!
・患者が飲んでいる精神科の薬がわかるようになりたい !
・精神疾患について緊急性の判断だけでもできるようになりたい!
初期研修医が知っておきたいこと・つまづきがちなところを1冊に凝縮。うつ病やBPSDなどへの初期対応や薬の飲み合わせなど,基本的な知識や対応を簡潔に解説。具体的なケースや処方例を取り上げているので現場での動き・対応がイメージしやすく,即実践に活かせる内容となっている。
現場で困らないための必読書!
