
脳神経外科 Vol.47 No.5
2019年05月発行
-
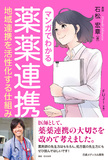
マンガでわかる薬薬連携
地域連携を活性化する仕組み
「いろいろな薬局からたくさん届くFAXどうにかならないかなぁ」「薬局から患者さんの情報提供がもう少しあれば嬉しいんだけどなぁ」といった病院の悩み。「病院の先生は忙しいから何度も電話をかけるのは気が引けるわ」「送ったFAXちゃんと確認してもらえたのか不安だな」といった調剤薬局の悩み。薬薬連携で、そんな悩みありませんか?本書は薬薬連携の課題とその解決方法を探るために、IT会社社長も務める現役医師が書いた書籍です。
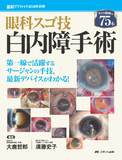
≪眼科グラフィック2018年別冊≫
眼科スゴ技 白内障手術
WEB動画付き 75本 第一線で活躍するサージャンの手技、最新デバイスがわかる!
【ほかでは読めない手技やデバイスが満載!】
第一線で活躍するサージャン独自の手術手技や、最新デバイスの知識・使い方 を「スゴ技」として厳選紹介。さらに、核片やIOLが落下した場合の処理など、本書でしか読めない新たな項目も追加。

実験医学 Vol.37 No.9
2019年6月号
【特集】細胞内の相分離
【特集】細胞内の相分離 核小体・Pボディ・ストレス顆粒など「膜のないオルガネラ」はどのように作られ凝集するのか.転写活性化メカニズムから神経変性疾患発症にも関わる生物学の新概念を紹介.話題の「相分離」を本邦初特集!
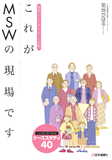
これがMSWの現場です
医療ソーシャルワーカーの仕事 心に寄り添う技術:ケーススタディ40
【本編より】患者さんが安心して病院にかかれて,困ったときには医療ソーシャルワーカーのところに相談に行けば大丈夫だと思ってもらえたら, 医療ソーシャルワーカーが専門職としての役割を果たしていることの証になると思います。
★MSW(医療ソーシャルワーカー)とは患者の「現実」と向き合う仕事です。MSW を目指す人,MSW の新人あるいは仕事に行き詰まっている中堅,MSW と同様の仕事をする事務職員や看護師等――に向け「現実」とどう向き合い,いかにより良い「現実」に変えていくか,具体的ノウハウを示した実践入門書です。
★① MSW になる方法・勉強法,②基本的な心得・知識・ノウハウ,③実際の仕事のディテール(40 事例)とその対処法,④ワンランク上のMSW になるための秘訣――を,実務経験豊富なMSWの第一人者が明快に解説しています。
★病院の医療相談室に持ち込まれる様々な相談やトラブル,それにより巻き起こる,患者や家族,医師,看護師などとの様々な人間模様を紹介します。患者とその家族が求める真の救いとは何か――MSW に最も大切な現場の経験知が凝縮されています。
■第1章~第3章では,「MSWとはどんな仕事か」,「MSWに求められる基本的心得・知識・ノウハウ」,「MSWになるための勉強・資格取得・就職の方法」を,体系的にわかりやすく紹介・解説。MSWを目指す人にとっては絶好の入門書となっています
■第4章「実践編」では,病院の医療相談室で実際に著者が体験した40の相談事例のディテール(様々なトラブルや悩み,その対処法と解決法,経過と顛末)を臨場感溢れる読み物形式で紹介します。そのまま実践対応が可能なMSWの貴重な経験知が凝縮されています。

クリニック・マネジメント入門
クリニックを「プロ集団」に変える33の秘訣
スタッフの「採用」「教育」「意識改革」「人事評価」「労務管理」から,クリニック全体の「経営」「ビジョン」「イメージ戦略」まで,その改善のテクニックを明快解説!
★クリニックの経営改善を多数成功させてきたクリニック専門の経営コンサルタントが,企業秘密とも言うべき最新ノウハウとその秘訣のすべてを伝授します!
★クリニック経営で最も大切なこと,それは院長自らも含めたスタッフの活性化です。前向きな改善・改良の意識,協力・協働の意識を醸成することによって,個々のスタッフの技能が自律的に向上し,クリニック全体の機能と経営力が向上するのです。――それが,クリニックの成功と失敗を分ける最大の分岐点となります。
★多くの院長の頭を悩ませるスタッフ・マネジメントについて,単に理念を唱えるのではなく,実際に効果が証明された様々な取組みや工夫を,自院ですぐ応用できるよう,実事例に沿って具体的かつ実践的に解説しています。

医療事故ゼロのための60の鉄則
事例・判例から学ぶケーススタディ60
★「医療事故情報センター」で理事長を務め,医療事故・訴訟に精通する著者が,医療スタッフであれば誰でも遭遇しそうな60 事例を厳選!全医療スタッフにとって必読の情報が満載されています。
★医療事故・訴訟の概要(経過・結果,判決内容等)をわかりやすく解説するとともに,医療現場の様々なケースに応じた60 の事例ごとに「教訓」をピックアップ! 医療事故を予防し,訴訟に陥らないためのポイントが明快に理解できます。
★全医療機関で役に立つ,医療事故予防のための対策・手法を図表・イラスト等を用いてわかりやすく紹介! 医療機関のための医療事故予防マニュアルとしても役立ちます。

がん看護 Vol.24 No.4
2019年5-6月
やっぱり現場がスキ!
やっぱり現場がスキ! がんの医学・医療的知識から経過別看護、症状別看護、検査・治療・処置別看護、さらにはサイコオンコロジーにいたるまで、臨床に役立つさまざまなテーマをわかりやすく解説し、最新の知見を提供。施設内看護から訪問・在宅・地域看護まで、看護の場と領域に特有な問題をとりあげ、検討・解説。告知、インフォームド・コンセント、生命倫理、グリーフワークといった、患者・家族をとりまく今日の諸課題についても積極的にアプローチし、問題の深化をはかるべく、意見交流の場としての役割も果たす。

2025年へのロードマップ 2014年4月補訂版
10年後の医療地図を探る 医療計画と医療連携の最前線
厚労省の2025年改革シナリオにより迫り来る医療の変革の波。
10年後の医療の有り様を的確に見通す1冊!!
★社会保障・税一体改革において厚労省が示した「2025 年の改革シナリオ」によって,医療と介護は今,大きな変革の時を迎えています。
★「2025 年の医療と介護のあるべき姿を一言で言えば『病院から地域へ』の転換だ」(本書より)。――2013 年から始まる新医療計画の方向性について,厚労省の「医療計画の見直し等に関する検討会」で座長を務めた著者が,2025 年の医療と介護の有り様とそこに向けたロードマップを示します。
★「医療計画」と「連携」――それがロードマップのキーワードです。政策誘導による「医療計画」と,診療報酬改定など経済誘導による「連携」(地域連携,医療・介護連携,多職種連携,チーム医療)の2つの視座から,10 年後の医療・介護の方向性とそのディテールを見通します。
★どの道がどこへ通じているのか,交差点を右折するのか左折するのか,どの道が通行止めか――を知る2025 年に向けた医療ロードマップ!!
◆CONTENTS◆
第1章
1.社会保障と税一体改革と「連携」 2.地域包括ケアシステム 3.医療と介護の連携 他
第2章
1.入院基本料と看護 2.LTAC(長期急性期医療) 3.精神科入院医療の見直し 他
第3章
1.医療計画の見直し検討会 2.医療圏見直し 3.数値目標とPDCAサイクル 他
第4章
1.2012年診療報酬改定と地域連携クリティカルパス 2.がんの連携パス 3.CKDの連携パス 他
第5章
1.薬局連携 2.歯科連携 他

臨床雑誌内科 Vol.123 No.5
2019年5月号
肝臓病学の未来
肝臓病学の未来 1958年創刊。日常診療に直結したテーマを、毎号"特集"として掲載。特集の内容は、実地医家にすぐに役立つように構成。座談会では、特集で話題になっているものを取り上げ、かつわかりやすく解説。

臨床雑誌外科 Vol.81 No.6
2019年5月号
肝胆膵外科の臨床研究update 2019
肝胆膵外科の臨床研究update 2019 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

Quality Indicator 2018 [医療の質]を測り改善する
聖路加国際病院の先端的試み
医療者にとって最大の使命である医療の質改善は、終わりのない旅。
改善に向けて歩み続ける路加国際病院の14年間にわたるQIの経年変化、改善活動を収載!「医療の質」改善を目指す病院が急増する今、手引きとなる一冊。
病院・医療法人経営者・管理者など、病院経営・管理に携わる方々に必読の書!!
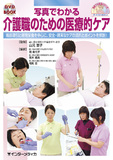
写真でわかる介護職のための医療的ケア
喀痰吸引と経管栄養を中心に、安全・確実なケアの流れとポイントを解説!
約230点の写真と動画(26分)で、根拠にもとづいた医療的ケアの確かな手技を実践的に解説!!
2012年の法改正により介護職の業務として認められた「喀痰吸引」と「経管栄養」の2つの医療的ケア。
実施にあたってリスクと責任の伴うこれらケアの基本手技とポイントから、「なぜそうするのか」の根拠まで、書籍と動画(26分)で丁寧に解説します

INTENSIVIST Vol.11 No.2 2019
2019年2号
特集:栄養療法アップデート 前編
特集:栄養療法アップデート 前編
Intensivist誌では,第42,43号において,以前11号で取り上げたテーマ「栄養療法」をアップデートします。栄養療法は現在では,単独では患者生命予後を変えるだけの力がなくなったのかもしれません。しかし患者生命予後改善まで結びつかずとも,生理学的・代謝栄養学的なアウトカムが改善することも重要であることが強調されてきており,栄養療法の立ち位置は高まる可能性を秘めています。本特集では,急性期栄養療法において,現状までにわかっていることとわかっていないことを明確にしたうえで,残されている課題,および重症患者における侵襲メカニズム,栄養障害の病態生理を解説します。

LiSA 2019年別冊春号
2019のシェヘラザードたち
2019のシェヘラザードたち

Heart View Vol.23 No.5
2019年5月
【特集】心臓リハビリテーション 患者別のシミュレーションで考える治療戦略
【特集】心臓リハビリテーション 患者別のシミュレーションで考える治療戦略

臨床画像 Vol.35 No.5
2019年5月号
【特集】前立腺癌の画像診断 update
【特集】前立腺癌の画像診断 update

関節外科 基礎と臨床 Vol.38 No.5
2019年5月号
【特集】透析関連の整形外科疾患 病態と治療
【特集】透析関連の整形外科疾患 病態と治療

腎臓病診療でおさえておきたいCases36
研修医や若手腎臓内科医が日常診療のなかで「どうしたらいいのか?」と疑問を感じたり、迷ったりするトピックスを抽出。それらに示唆を与える36症例を厳選して解説を展開する。慶應大学で診療を受けた患者の長年にわたるデータと腎生検所見の蓄積は極めて貴重。腎臓内科医が臨床で必要とされる知識や判断基準を症例から読み取り実践できるよう、オール慶應の執筆陣が丁寧に症例を読み解く!

J-IDEO Vol.3 No.3
2019年5月号
【Special Topic】感染症検査機器の最新潮流
【Special Topic】感染症検査機器の最新潮流 本号のスペシャルトピックは「感染症検査機器の最新潮流」.
飛躍的な技術の進歩によってパラダイムシフトが起こりつつある感染症検査領域.今回は大楠清文先生に感染症検査機器の最新動向,上手な付き合い方,ピットフォールなどを解説して頂きます.
また最新の情報をお届けするHOT TOPICでは,第一世代セファロスポリン抗菌薬の供給不足における対応策について紹介します.
