
臨床眼科 Vol.72 No.9
2018年9月号
特集 第71回 日本臨床眼科学会講演集[7]
特集 第71回 日本臨床眼科学会講演集[7] -

臨床外科 Vol.73 No.9
2018年9月号
特集 癌手術エキスパートになるための道〔特別付録Web動画付き〕
特集 癌手術エキスパートになるための道〔特別付録Web動画付き〕 外科学において診療,教育,研究が重要であることは言うまでもない.そして診療の分野においては,医療倫理も含めた患者さんへの温かい対応,豊富な知識に基づいた適切また的確な判断,そして優れた医療技術は,それを支える大きな柱である.特に外科医においては,手術手技も含めた高度な技術によって,その診療は遂行される.一方,これらの手術技術の修得は,多くの先輩から後輩への指導とそれによる経験の蓄積,そして学術集会や論文,さらには手術見学などの機会を通した見聞によって,時を重ねつつ成し遂げられる.これら手術技術の修得を,より速やか,かつ着実に身に付ける方策を,自身の経験を通して,もしくは自身が展開する教育法などの観点から,各分野におけるエキスパートの先生に,若き前途洋々の外科医への提言をご執筆いただいた.本特集が,若き外科医もしくは若手外科医の教育に携わる先生方の「道標」となり,ひいてはわが国の外科医療のさらなる発展に寄与することを願うものである.

精神医学 Vol.60 No.8
2018年8月号
特集 作業療法を活用するには
特集 作業療法を活用するには -

脳神経外科 Vol.46 No.8
2018年8月号
-

公衆衛生 Vol.82 No.9
2018年9月号
特集 日本におけるWHO協力センター
特集 日本におけるWHO協力センター -
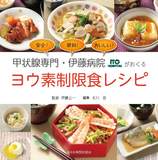
甲状腺専門・伊藤病院がおくる ヨウ素制限食レシピ
甲状腺疾患の検査・治療において欠かせないヨウ素の制限。甲状腺専門病院の伊藤病院で実際に使用されているバラエティに富んだヨウ素制限食を、自宅で簡単に美味しく作れるレシピ集です。巻末付録としてバセドウ病、甲状腺がんの制限食品一覧付き!

異常心電図 ミネソタコードと臨床 改訂第5版
心電図自動診断の正しい解釈
本書は,心電図の波形分類に本邦でゴールドスタンダードとなっているミネソタコードについて,基本となる心電図波形の計測法をはじめ,それら心電図波形が臨床的にどのような意味をもっているのか,チェックされた波形の指導区分にランクづけするにはどうしたらよいかを中心に解説した.
心電図波形はEinthovenの時代から長い間,横軸は太く縦軸は細い線という伝統的な記録法で描かれてきた.このアナログ波形を基盤として完成したのがミネソタコードである.一方,自動解析心電計が描く心電図はサーマルレコーダーによるため,一様の細い線で描かれている.とはいっても,急峻な振れは細めに,緩徐な振れは太めになっている.サーマルレコーダーは元来はアナログである心電図をデジタル変換して取り出したデータを波形分析後,見た目にはアナログ波形らしく描いているのであって,言わば偽物の心電図である.その意味では,自動解析心電図が描いた波形をミネソタコードの計測方式で再検討するわけにいかず,あくまでも自動解析結果を鵜呑みにせざるをえないとも考えられる.
しかし,パターン認識を苦手とする自動解析心電計には弱点がある.たとえばST部の上り坂と下り坂の判別には誤りが多く,ST・Tに重なったP波の認識もできないことが多い.まして心電図には記録されない静脈洞結節の興奮・伝達異常という専門医でも診断困難な不整脈に対しては,解析プログラムすらないのが現状である.このため,自動解析心電計がタイプアウトした結果については医師があらためて再検討する必要があるが,本書がその時の参考に役立てば幸いである.

訪問リハビリテーション アドバイスブック
訪問リハにすでに携わっている,またはこれから新たに携わる理学療法士(PT),作業療法士(OT)にむけて,現場での応用力・柔軟性・実践力を養うことを目指し,詳細な知識・技術を解説した書。
訪問現場で活躍しているセラピストを中心に,医師,看護師,介護福祉士,歯科衛生士,薬剤師,管理栄養士,保健師,義肢装具士,社会福祉士,介護支援専門員や相談支援専門員といった訪問リハにかかわるさまざまなスタッフにより,多職種にまたがる知識や技術をまとめている。また,日本各地であらゆる経験をしている著者のコラムも添え,現場の実例から学んだ実践的な臨場感を事例として提示している。

≪形成外科治療手技全書 II≫
形成外科の基本手技2
形成外科治療手技全書の中でも最も基本的な手技を解説。本書はその2で皮弁・組織弁を解説する。議論の多い皮弁について、歴史的背景を踏まえて系統立てて分類し解説した。

図表でわかる
無痛分娩 プラクティスガイド
無痛分娩を安全に行うために必要な知識を凝縮したガイドブック。項目タイトルを質問方式とし,各パート見開き2ページを原則とした構成。麻酔の効果範囲などを立体的に意識できるイラストによる解説やマトリクスを多用して,視覚的に理解できるようになっている。
無痛分娩を初めて行う者が手技を習得するために予習として読めるのはもちろん,今まで無痛分娩を行ってきた者にとっても,手技の見直し,および「無痛分娩とはなにか」「無痛分娩をより安全に行うためには」ということへの根本的な理解を助ける書籍である。

LiSA 2018年別冊春号
2018のシェヘラザードたち
2018のシェヘラザードたち

検査と技術 Vol.46 No.9
2018年9月号
特集 現場で“パッ”と使える免疫染色クイックガイド
特集 現場で“パッ”と使える免疫染色クイックガイド -

臨床皮膚科 Vol.72 No.9
2018年8月号
-

臨床整形外科 Vol.53 No.8
2018年8月号
誌上シンポジウム 椎弓形成術 アップデート
誌上シンポジウム 椎弓形成術 アップデート -
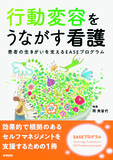
行動変容をうながす看護
患者の生きがいを支えるEASEプログラム
患者の生きがいを支え、効果的で根拠のあるセルフマネジメントを支援するための1冊。EASEプログラムとは、Encourage Autonomous Self-Enrichment programの略で、対象者の生活重要事を前景化させたうえで、保健行動モデルなどを活用し、対象者の理解とアセスメントを行い、行動変容を支援するプログラムである。行動変容に関する基礎知識や支援する技法を解説し、さらにこれを活用した事例を紹介する。

MEA マイクロ波子宮内膜アブレーションの臨床
過多月経の外科的療法として注目される,マイクロ波子宮内膜アブレーション(MEA)を行うために必要なセットアップ・機器の紹介から手技までを1冊で学べる書籍。詳細で平易な解説,患者に説明するためのインフォームドコンセント用の資料ページ, MEA施行のためのガイドラインを付録し,本書一冊で外来から手術までMEA導入における一通りの準備ができるようになっている。

心疾患合併妊娠の管理
心疾患合併妊娠の妊婦管理は増加傾向にあり,心疾患の専門家でなく一般的な産科医においても,その知識は必須なものとなりつつある。具体的な症例,典型例を提示しながら,その経過と処置,注意点,転機と予後を時系列に追うことで解説の意味を深め,わかりにくいところはQ&A方式での記載などを用いて可能な限り平易に解説している。
産婦人科医のための心疾患合併妊娠の周産期管理指針となる一冊。

LiSA Vol.25 No.5 2018
2018年5月号
徹底分析シリーズ:ダブルルーメンチューブ/症例カンファレンス:冠動脈3枝病変を有する患者の進行性胃癌/異国交流インタビュー in English:日本の無痛分娩の将来は?Dr. William Camannに聞く②
徹底分析シリーズ:ダブルルーメンチューブ/症例カンファレンス:冠動脈3枝病変を有する患者の進行性胃癌/異国交流インタビュー in English:日本の無痛分娩の将来は?Dr. William Camannに聞く②

LiSA Vol.25 No.6 2018
2018年6月号
徹底分析シリーズ:術前内服薬はそれでいいのか?/止めてはいけない理由,続けてはいけない理由を知る/症例カンファレンス:重度肥満患者の巨大卵巣腫瘍摘出術/異国交流インタビュー in English:日本の無痛分娩の将来は?Dr. William Camannに聞く③
徹底分析シリーズ:術前内服薬はそれでいいのか?/止めてはいけない理由,続けてはいけない理由を知る/症例カンファレンス:重度肥満患者の巨大卵巣腫瘍摘出術/異国交流インタビュー in English:日本の無痛分娩の将来は?Dr. William Camannに聞く③

LiSA Vol.25 No.4 2018
2018年4月号
徹底分析シリーズ:術前診察 基本の「き」/症例カンファレンス:気管支喘息とコントロール不良の甲状腺機能亢進症を有する卵巣癌患者/異国交流インタビュー in English:日本の無痛分娩の将来は?Dr. William Camannに聞く①
徹底分析シリーズ:術前診察 基本の「き」/症例カンファレンス:気管支喘息とコントロール不良の甲状腺機能亢進症を有する卵巣癌患者/異国交流インタビュー in English:日本の無痛分娩の将来は?Dr. William Camannに聞く①
