
カラーアトラス疣贅治療考 いぼ/コンジローマ/みずいぼ
・本邦初の定本―いぼ治療のすべてを網羅した実践書. ・カラー写真495枚によるアトラスの決定版. ・皮膚科医,産婦人科医,泌尿科医,一般外科医,形成外科医に必携の臨床書.

肝臓クリニカルアップデート 2025年12月号
2025年12月号
特集:肝細胞癌に対する根治をめざした薬物療法の進歩 ─コンバージョン治療を含めて─
特集:肝細胞癌に対する根治をめざした薬物療法の進歩 ─コンバージョン治療を含めて─

画像診断 Vol.45 No.14(2025年12月号)
【特集】WHO分類(第5版)に基づく骨軟部腫瘍の画像診断update
【特集】WHO分類(第5版)に基づく骨軟部腫瘍の画像診断update 『WHO分類第5版』に基づき、骨軟部腫瘍の最新知見を整理。鑑別すべき良性病変や転移性腫瘍の画像診断も網羅し、病理・放射線・整形外科・腫瘍内科の各視点から、診断から集学的治療までをアップデートできる必携の一冊!

臨床放射線 Vol.70 No.6
2025年11・12月号
小児放射線 診断と治療アップデート
小児放射線 診断と治療アップデート
本号の特集は「小児放射線 診断と治療アップデート」です。小児は放射線感受性が高く生涯にわたっての発がんリスクも高いうえ、近年は虐待疑い患者への対応も重要となっていることから、知識と対応のアップデートが欠かせません。本特集に寄せられた貴重な総説を読み込み、小児放射線医療に関し認識を新たにしていただければ幸いです。多彩な領域から投稿されてきた論文14篇、好評連載「今月の症例」ともども、是非ご一読ください。

臨床画像 Vol.41 No.12
2025年12月号
【特集】核医学による代謝機能画像(診断)から治療へ−ヨード内用療法からPSMAまで−
【特集】核医学による代謝機能画像(診断)から治療へ−ヨード内用療法からPSMAまで−

レジデントノート増刊 Vol.27 No.11
【特集】がん診療でよく出合う困りごとに対応できる研修医になる!
【特集】がん診療でよく出合う困りごとに対応できる研修医になる!
がん診療で遭遇する多くの有害事象を徹底解説します.がんそのものによる疼痛などの症状に加え,抗がん剤による消化器症状や骨髄抑制による発熱性好中球減少症など,適切な初期対応が必須となる場面を重点的に解説.また,免疫チェックポイント阻害薬特有のirAE(免疫関連有害事象)についてもとりあげます.さらに,緩和ケアで悩みがちなオピオイドの安全な使用法,終末期の看取り,患者・家族へのコミュニケーションなど,がん診療にかかわる研修医が知っておきたい知識を凝縮した一冊です.

がん薬物療法副作用管理マニュアル 第3版
副作用の重症度評価、原因薬の中止や減量、支持療法などの適切な対応をサポート!
がん薬物療法で直面する有害事象をテーマに、その早期発見、重症度評価、原因薬の中止や減量、支持療法など、臨床で役立つポイントをギュッと凝縮。原因薬と発現割合、好発時期、リスク因子の他、irAEの情報も充実。症状別の各論では「抗がん薬の副作用が疑われた症例」「それ以外の原因が疑われた症例」の2パターンを掲載。総論では新たに「生殖機能(妊孕性)低下」と「外見の変化(アピアランスケア)」の章を立項した。

レジデントノート Vol.24 No.18
2023年3月号
【特集】救急・病棟でデキる!糖尿病の診かたと血糖コントロール
【特集】救急・病棟でデキる!糖尿病の診かたと血糖コントロール 高血糖緊急症にどう対応する?周術期の血糖管理は?教育入院って?最新のデバイスとは?など,研修医がいま知りたい糖尿病診療の知識をやさしく解説.患者さんの抱える想いや暮らしも考えた診療の進め方が学べます.
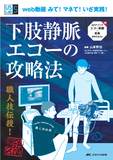
≪US Labシリーズ 5≫
web動画 みて! マネて! いざ実践!
下肢静脈エコーの攻略法
【職人技が確実に身につく静脈エコーの必読本】
現場で豊富な知識と技術を身に付け “エコー職人”と評される著者が、下肢静脈エコーの最新のガイドラインを交えながら、長年の技師としての視点から、わかりやすく丁寧に静脈エコーのすべてを解説。画像と走査が一画面になった動画で、職人の動きも学べる。

≪こころJOB Books≫
心のケアにたずさわる人が知っておきたい精神系のくすり
【臨床でよく出合う80薬剤が基礎からわかる】
精神科治療の重要な柱である薬物療法について「どうしてこの薬を投与するの?」といった基礎から解説。精神療法やカウンセリングと組み合わせることでどういった効果が考えられるかも紹介する。病院で働くスタッフだけでなく、心理的なケアにかかわるすべての人に必携の書。

レジデントノート Vol.24 No.7
2022年8月号
【特集】めまい診療 根拠をもって対応できる!
【特集】めまい診療 根拠をもって対応できる! もう“めまい診療は苦手”とは言わせない!BPPV,前庭神経炎,脳梗塞など救急でよく出合うめまいの原因疾患について,病歴聴取や身体診察のポイント,治療法を解説.病態を意識した適切な対応が身につく!

消化管吻合法バイブル [Web動画付]
器械吻合が広く普及する一方、技術さえ習得すれば手縫い吻合のほうが安全で柔軟性に富んでおり、信頼性が高いケースも少なくない。また腹腔鏡、胸腔鏡手術の普及により、熟練した施設では器械吻合をどのように行っているか関心が高まっている。本書では、開腹下での手縫いの吻合、開腹下での器械吻合、内視鏡下での器械吻合を網羅。エキスパートの消化器外科医がどのような吻合を行っているかを動画とともに明らかにする。

小児科診療ガイドライン 第5版
最新の診療指針
●小児科疾患診療のゴールデンスタンダードが満載の必携書、4年ぶりの改訂!
●好評書籍「小児科診療ガイドライン」がさらにブラッシュアップされて登場。小児科医がカバーする広い範囲の症状・疾患について、最新の診断と治療の指針を掲載しました。臨床現場に欠かせない一冊です。

助産雑誌 Vol.79 No.6
2025年 12月号
特集 飛ぶ無痛Caféコラボ! 無痛分娩のアクティブバース 動ける麻酔と動かす助産
特集 飛ぶ無痛Caféコラボ! 無痛分娩のアクティブバース 動ける麻酔と動かす助産 かつてない少産化の今、産み育てることに関わる意識や言葉、制度や環境が大きな変革期を迎えています。新しい助産師像を模索する現代の助産師、そして妊娠・出産・育児を考える全ての人と共に、考え、つくる雑誌です。 (ISSN 1347-8168)
隔月刊(偶数月)、年6冊

≪小児科ベストプラクティス≫
小児急性脳炎・脳症のとらえ方と治療戦略―Practice and Progress
日本がリーダーシップをとり,常に牽引しつづけている小児急性脳炎・脳症.
ガイドラインをさらに踏み込んだエキスパートコンセンサスが蓄積され,研究・臨床の最新知見,有効性を示す症例を収載.さまざまな疾患・病態に起因し診断が難しい急性脳症の要点を「診断のポイント」で解説,難治性が多く家族への伝え方が難しい「家族への説明」を語り口調で紹介.

緩和ケア Vol.35 No.6
2025年11月号
【特集】症状・ケアニーズを捉える呼吸器疾患のアドバンスト緩和ケア
【特集】症状・ケアニーズを捉える呼吸器疾患のアドバンスト緩和ケア
「非がん性呼吸器疾患の緩和ケア」について、多くの医療従事者はその重要性を認識しているだろう。だが、がん患者のそれと比較してエビデンスや実践的な知見は十分に体系化されていない。それぞれの疾患の経過、患者の症状、ケアニーズは多様で複雑なのである。標準治療が進歩する一方で、QOLを維持・向上するための「非がん性呼吸器疾患の緩和ケア」の重要性は高まっている。
本特集では、それぞれの疾患特有の経過や治療の基本、患者の多面的な苦痛への具体的な実践をまとめ、患者のセルフケアなど、医療者が知っておくべき知識とスキルを網羅的に紹介する。

骨転移診療プラクティス&ケースファイル
実践知とケースで臨床力をアップしよう!
『骨転移診療ガイドライン(改訂第2版)』の内容に基づきながら具体的な診療の手順や対応・コツをまとめた,臨床現場で真に役立つ実践書.骨転移の診断から治療薬の使い方,合併症マネジメント,整形外科的介入,放射線治療,リハビリテーション,緩和ケアについて,Scene別/ビジュアルガイド/ケースファイルの3章立てで解説.診療科や職種を超えたプラクティスを伝え,骨転移診療の質の底上げを実現する一冊.

関節外科 基礎と臨床 Vol.43 No.4
2024年4月号
【特集】インプラント周囲骨折の治療 成功へ導く最新の知見
【特集】インプラント周囲骨折の治療 成功へ導く最新の知見

心エコー 2025年11月号
心アミロイドーシスのCutting Edge
心アミロイドーシスのCutting Edge 特集は「心アミロイドーシスのCutting Edge」.心アミロイドーシス総論─そもそもアミロイドとは何か?/心アミロイドーシスは意外に拘束性心筋症ではない?/Apical sparingはどれほどお値打ちか?/マルチモダリティイメージングの有用性を識る/心アミロイドーシス治療の現状と今後の展望 等を取り上げる.連載として,症例問題[Web動画連動企画]高齢者にみられた大動脈弁疾患の1例,Something new, Something special,伊藤 浩の3分で読める!イイ話等を掲載.

心エコー 2025年10月号
非心臓手術における術前評価にどう応える?
非心臓手術における術前評価にどう応える? 特集は「非心臓手術における術前評価にどう応える?」.非心臓手術の術前評価に心エコーは必要か?/虚血性心疾患患者の術前評価/大動脈弁疾患患者の術前評価/僧帽弁疾患患者の術前評価/一次性心筋症患者の術前評価/二次性心筋症患者の術前評価/ハイリスクの高齢者の術前評価 等を取り上げる.連載として,症例問題[Web動画連動企画]心房性の三尖弁逆流?,留学のススメ,Echo Trend 2025,伊藤 浩の3分で読める!イイ話等を掲載.
