
増補版 遺伝性出血性末梢血管拡張症(オスラー病;HHT)の診療マニュアル
遺伝性出血性末梢血管拡張症(オスラー病;HHT)に関する国内の報告、診療指針等をまとめたマニュアルの増補版.
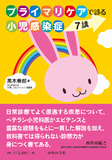
プライマリケアで診る小児感染症 7講
ベテラン小児科医が,感冒・インフルエンザ・易感冒など,小児プライマリケアで日常的に接する感染症を中心とした疾患について,豊富な経験から得た診療ノウハウを伝授する.

日常診療のための検査値のみかた
医学の各領域で日常的に使用される検査値の臨床的意義や,診断プロセスにおける基準値や異常値のみかた考え方,また検体採取のノウハウなどについてわかりやすく解説した.

よくわかる精神科治療薬の考え方,使い方 3版
精神科における的確な薬物治療を行ううえで,どの薬剤をどういった考えで選び,どのように使えばいいのかを平易に解説した書の改訂3版.項目自体も一部見直しをはかり,最新の知見を盛り込んだ.薬剤についてのみならず,各疾患のポイントや患者・家族に対する説明など,できるだけ具体的に解説した.精神科医のみならず,看護師,薬剤師,臨床心理士などの医療従事者にとってもわかりやすいテキストとする.

白血病診療Q&A
一つ上を行く診療の実践
白血病診療の現場で出会う様々な問題点,疑問点,トラブルなどをQ&A形式で解説.既存ガイドラインだけではまかなえない,臨床の現場で必要な知識が詰まった1冊.

リハビリテーションのための臨床神経生理学
臨床神経生理学は難しいわりに,リハビリテーションに直接使えない…と思っている人は多いのではないだろうか.本書は,臨床神経生理が疾病や障害の理解をより深め,実際のリハビリにとても役立つツールであることを示している.初学者や,苦手な人にも理解しやすいよう,少しでも耳慣れないワードには注釈を付け,平易に解説した.一読すればきっと,「これなら自分でもできる」と自信が付く.明日からのリハビリが変わる一冊だ.

触れてわかる腰痛診療<画像でわからない痛みをみつけて治療する>
適切な外科手術が行われても,腰痛が残って苦しんでいる患者や,画像診断では原因が特定できない腰痛に悩む患者が少なからず存在する.本書では,そういった非特異的腰痛について,手で身体に触れる診察法と治療を紹介.身体に触れることで,個々の患者の痛みの本質が見えてくる.どこのポイントをどう押して動かせばいいのか,豊富なイラストを使って解説.専門医ではなくとも分かりやすい,今日から早速使える技術を習得できる.

本当にあった医学論文2
驚きの症例報告,ふとした疑問を大真面目に調べた臨床試験,臨床に役立つ(かもしれない)論文など,実在するふしぎな医学論文の数々を紹介した好評書の第二弾.

甲状腺疾患のクリニカルクエスチョン レジデントの疑問に答えます
研修医や若手スタッフが困ったこと,疑問に思っていることを実際に聞き込み,平易な解決策を紹介.明日からの甲状腺疾患診療に自信がつく1冊だ.

研修医のための輸液・水電解質・酸塩基平衡
臨床に応用するための水電解質・酸塩基平衡の基本を,日々の臨床経験を踏まえて,本格的にわかりやすく解説する.研修医,救急医はもちろん,すべての医療者必読の1冊!

EBMがん化学療法・分子標的治療法2016-2017
今日のがん化学療法・分子標的治療における代表的な文献,各種トライアルに基づき,EBMの実践のため,現状における診療の指針や方向性を示す実践的な臨床書.テーマに関連する代表的かつ具体的なエビデンスを挙げ,今日の時点における最新のコンセンサスや治療法,根拠となった臨床研究の問題点や限界,本邦の患者に適用する際の注意点など,現場で判断に迷うような事柄を解説し“がん治療”の方向性を指し示す内容となっている.

ギャンブル依存症 サバイバル
パチンコ・スロット・競馬・競輪におぼれる人を救済するため、患者・家族・医療者に贈る指南書
治療の共通基盤となる最新の知識から,具体的な臨床技法,当事者の体験談を通じて得られた知見などをわかりやすく紹介する.ギャンブル依存症克服のためのバイブル!

骨折の機能解剖学的運動療法 その基礎から臨床まで 体幹・下肢
骨折の運動療法を行うために必要な最低限の知識を総論で網羅.各論では骨折後に必発の組織の修復過程を基礎に疫学、整形外科的な治療の考え方、評価と治療について解説.

骨折の機能解剖学的運動療法 その基礎から臨床まで 総論・上肢
骨折の運動療法を行うために必要な最低限の知識を総論で網羅.各論では骨折後に必発の組織の修復過程を基礎に疫学、整形外科的な治療の考え方、評価と治療について解説.

産業医・労働安全衛生担当者のためのストレスチェック制度対策まるわかり
いよいよ,従業員50人以上の事業場にストレスチェック制度が義務化されます.「ストレスチェックって何? 何を調べるの?」「実施しなかったら,何か会社に不利益があるの?」「どんな業者に頼めばいいの?」そんなあなたの疑問に,日本ストレスチェック協会のプロ集団がズバリ! 回答します.ストレスチェック制度対策は,この1冊でまるわかり!

jmedmook57 あなたも名医!スキルアップをめざす糖尿病薬物治療
■わが国で糖尿病が疑われる患者は2016年に1000万人を超え、国民病とも言われる状況になっています。
■糖尿病関連の各種ガイドラインの内容から一歩踏み込んだ診療を実践したい先生方に贈る「スキルアップのための糖尿病薬物治療」のガイドブックです。
■糖尿病非専門医が日常診療で抱く様々な疑問に対し、診療に精通した専門家たちが具体的に解説。公式ガイドラインでは知ることのできない診療ノウハウをお伝えします。
■各薬剤の適応・使用法のほか、合併症ごとの薬剤の最適選択、患者さんからの疑問に答えるQ&Aなど盛りだくさんの実践的内容は、明日からの糖尿病診療に必ず役立ちます!

糖尿病と骨粗鬆症
治療薬を考える
●糖尿病やその合併症(動脈硬化、高血圧など)と骨粗鬆症は、病態やリスク因子が複雑に絡み合い、糖尿病治療薬は骨代謝に、骨粗鬆症治療薬は糖代謝に影響を及ぼします。
●どちらも使う患者さんに対して医療現場では何に注意すればよいのか? 糖尿病や各合併症の骨粗鬆症への影響の仕方、それぞれの治療薬の作用メカニズムや代謝への影響・リスクについて、第一線の専門家が解説します。
●糖尿病と骨粗鬆症の包括的マネジメントに向けて、知識の整理に役立つ1冊です。
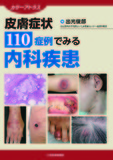
皮膚症状110症例でみる内科疾患
■皮膚科医でない医師が日常診療で皮膚症状と口腔粘膜症状をみたとき、どのような疾患を想起すべきか?
■見開き2頁で、疾患特有の皮膚症状(口腔粘膜症状)と,間違えやすい似たもの画像とを比較できるよう構成。
■この1冊で、皮膚症状と口腔粘膜症状を手がかりとして内科疾患を想起するための勘ドコロがわかります。
■110症例の皮膚(口腔粘膜)写真とツボを押さえたコンパクトな解説により、皮膚(口腔粘膜)症状から内科疾患にアプローチするポイントを押さえられます。プライマリ・ケア医、内科医、総合診療医必携の皮膚アトラス!
【内容】
第1章 心疾患と皮膚症状
第2章 悪性腫瘍と皮膚症状
第3章 膠原病・血管炎と皮膚症状
第4章 関節リウマチと皮膚症状
第5章 内分泌・代謝疾患と皮膚症状
第6章 腎臓疾患と皮膚症状
第7章 消化器疾患と皮膚症状
第8章 栄養障害と皮膚症状
第9章 肉芽腫性疾患と皮膚症状
第10章 感染症等と皮膚症状
第11章 性感染症/免疫不全と皮膚症状
第12章 薬剤副作用と皮膚症状
第13章 アナフィラキシー・蕁麻疹様症状を示す疾患と皮膚症状
第14章 妊娠に伴う皮膚疾患
第15章 内臓疾患と口腔粘膜症状
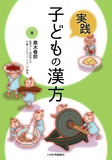
実践子どもの漢方
●「感冒」に抗菌薬は不要、がスタンダードとなりました。また、胃腸炎で吐き気止めを処方、果たして有効でしょうか。西洋薬で対応できないとき、効果が十分でないとき、西洋医学でその概念がない病態をみるとき、”漢方”という選択肢を持っていると診療の幅が広がります。
●近年注目されるシステムバイオロジー、マイクロバイオーム、個別医療と漢方の親和性についても解説しています。
●子どもの保護者の不調にも応えられる処方も掲載しました。
●頻用処方例および模擬症例で処方の実際がわかります。

小児発達障害について非専門医の先生に知っておいてほしいこと、まとめてみました
〇診療所で、学校検診の現場で、「あれ? もしかして発達障害かも?」と思ったときどうすればいいの?
〇専門医へ紹介する際に本人や保護者、学校教師にどのように説明すべきなの?
〇専門医にコンサルしたくても周囲に児童精神科専門医がいない!
そんな悩みに児童青年期精神医学に長年携わるエキスパートが答えます!
前半では現代における小児発達障害の概論を対話形式で解説し、後半は代表的な疾患の模擬症例を漫画で提示し、その疾患の概説、診断や専門医への紹介のポイントを解説。専門医での治療とその症例をご紹介しています。
研修医やプライマリ・ケア医、小児科医をはじめ、学校医、看護師など日々小児の診療にあたる医療従事者の方々に「発達障害について知っておいてほしいこと」まとめてみました。
