
LiSA Vol.24 No.11 2017
2017年11月号
徹底分析シリーズ:閉塞性睡眠時無呼吸/症例検討:予期せぬICU入室2
徹底分析シリーズ:閉塞性睡眠時無呼吸/症例検討:予期せぬICU入室2

LiSA Vol.24 No.10 2017
2017年10月号
症例検討:呼吸器疾患患者の周術期管理/症例検討:予期せぬICU入室 1
症例検討:呼吸器疾患患者の周術期管理/症例検討:予期せぬICU入室 1

LiSA Vol.24 No.9 2017
2017年9月号
徹底分析シリーズ:呼吸器疾患患者の周術期管理/症例検討:術前シミュレーション
徹底分析シリーズ:呼吸器疾患患者の周術期管理/症例検討:術前シミュレーション

LiSA Vol.24 No.8 2017
2017年8月号
徹底分析シリーズ:麻酔科×MBA/症例検討:鎮静
徹底分析シリーズ:麻酔科×MBA/症例検討:鎮静

LiSA Vol.25 No.1 2018
2018年1月号
徹底分析シリーズ:術後認知機能障害/症例カンファレンス:慢性血栓塞栓性肺高血圧症合併患者の横行結腸癌手術/異職交流インタビュー:『コウノドリ』との対話
徹底分析シリーズ:術後認知機能障害/症例カンファレンス:慢性血栓塞栓性肺高血圧症合併患者の横行結腸癌手術/異職交流インタビュー:『コウノドリ』との対話

LiSA Vol.24 No.7 2017
2017年7月号
快人快説:最先端の研究テクノロジー紹介③ CRISPR/Cas9によるゲノム編集/症例検討:血液疾患患者の麻酔/特集:はじめての国際学会<後編>
快人快説:最先端の研究テクノロジー紹介③ CRISPR/Cas9によるゲノム編集/症例検討:血液疾患患者の麻酔/特集:はじめての国際学会<後編>

LiSA Vol.24 No.6 2017
2017年6月号
快人快説:最先端の研究テクノロジー紹介② 質量顕微鏡/症例検討:デスフルランを使いこなそう 2/特集:はじめての国際学会<前編>
快人快説:最先端の研究テクノロジー紹介② 質量顕微鏡/症例検討:デスフルランを使いこなそう 2/特集:はじめての国際学会<前編>

LiSA Vol.24 No.5 2017
2017年5月号
徹底分析シリーズ:心臓麻酔ステップアップ:オフポンプ冠動脈バイパス術/症例検討:デスフルランを使いこなそう 1
徹底分析シリーズ:心臓麻酔ステップアップ:オフポンプ冠動脈バイパス術/症例検討:デスフルランを使いこなそう 1

LiSA Vol.24 No.4 2017
2017年4月号
徹底分析シリーズ:麻酔科医のプロフェッショナリズムを考える/徹底分析シリーズ:続 痛み治療の素朴な疑問に答えます 3
徹底分析シリーズ:麻酔科医のプロフェッショナリズムを考える/徹底分析シリーズ:続 痛み治療の素朴な疑問に答えます 3

LiSA Vol.24 No.3 2017
2017年3月号
徹底分析シリーズ:続 痛み治療の素朴な疑問に答えます 2/症例検討:腎機能低下患者の麻酔
徹底分析シリーズ:続 痛み治療の素朴な疑問に答えます 2/症例検討:腎機能低下患者の麻酔

LiSA Vol.24 No.2 2017
2017年2月号
徹底分析シリーズ:続 痛み治療の素朴な疑問に答えます1/症例検討:腰痛
徹底分析シリーズ:続 痛み治療の素朴な疑問に答えます1/症例検討:腰痛

LiSA Vol.24 No.1 2017
2017年1月号
徹底分析シリーズ:無痛分娩における麻酔科医の役割/症例検討:リスクのある妊婦の無痛分娩
徹底分析シリーズ:無痛分娩における麻酔科医の役割/症例検討:リスクのある妊婦の無痛分娩

実験医学 Vol.36 No.14
【特集】疾患を制御するマクロファージの多様性
【特集】疾患を制御するマクロファージの多様性 近年,組織特異的なマクロファージの発見が相次ぎ,それぞれの機能や疾患との関連が明かされはじめています.治療標的として期待されるマクロファージの「多様性」に迫る最新研究をご紹介します.

実験医学増刊 Vol.36 No.12
【特集】脳神経回路と高次脳機能
【特集】脳神経回路と高次脳機能 イメージングや光遺伝学など新たな解析技術により爆発的進歩を遂げた脳神経科学を総力特集!神経回路再編のメカニズムからヒトの心の源に迫る高次機能,精神・神経疾患まで,分野の最新像を29篇の総説で学べる

実験医学増刊 Vol.36 No.10
【特集】脂質クオリティ
【特集】脂質クオリティ 生体膜の構成成分・エネルギー源・シグナル分子など多彩な役割をもつ脂質の「質」(構成する脂肪酸や極性頭部の種類)に着目し,その多様性が関与する生命現象や疾患の制御から最新の分析技術まで幅広く解説しました.

レジデントノート増刊 Vol.20 No.5
【特集】循環器診療のギモン、百戦錬磨のエキスパートが答えます!
【特集】循環器診療のギモン、百戦錬磨のエキスパートが答えます! 現場でよく出合う疑問を厳選し,救急や病棟での急性期の初期診断・治療から慢性期の管理まで最新のエビデンスに基づいた循環器診療の重要ポイントを解説!「疑問」をアンカーに効率よく多くのことが学べる!

実験医学増刊 Vol.36 No.7
【特集】超高齢社会に挑む骨格筋のメディカルサイエンス
【特集】超高齢社会に挑む骨格筋のメディカルサイエンス 超高齢社会の日本では,筋肉の量や機能を維持し健康寿命を伸ばすことが社会的に求められています.本書では,筋萎縮・肥大のメカニズムから代謝・臓器連関・筋疾患研究まで,骨格筋研究の最新知見をご紹介します.
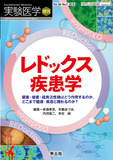
実験医学増刊 Vol.36 No.5
【特集】レドックス疾患学
【特集】レドックス疾患学 レドックス(酸化還元)分野ではよく知られている活性酸素に加え,近年,窒素・硫黄活性種など多彩な分子が関連する報告が相次いでいます.本書では,関連分子の代謝・シグナル制御から様々な疾患との関連まで,最新の知見を紹介します.

実験医学増刊 Vol.36 No.2
【特集】がん不均一性を理解し、治療抵抗性に挑む
【特集】がん不均一性を理解し、治療抵抗性に挑む がんの「ゲノム」と「機能」の不均一性は,がんが治療抵抗性を発揮する原因として考えられています.がん不均一性を克服するために,専門分野が様々な研究者集団が,どんな治療法を目指しているかをご覧ください.

Gノート増刊 Vol.5 No.2
【特集】動脈硬化御三家 高血圧・糖尿病・脂質異常症をまるっと制覇!
【特集】動脈硬化御三家 高血圧・糖尿病・脂質異常症をまるっと制覇! 高血圧・糖尿病・脂質異常症の診断と治療を,エビデンスに基づきポイントを押さえてわかりやすくまとめました.質の高い診療をめざす総合診療医・内科医・家庭医や,プライマリ・ケアに従事する医療職の方々におすすめ!
