
周産期医学48巻2号
2018年2月号
【特集】新生児の薬物療法―update
【特集】新生児の薬物療法―update

小児外科50巻2号
2018年2月号
【特集】先天性体表瘻孔のすべて
【特集】先天性体表瘻孔のすべて

小児内科50巻2号
2018年2月号
【特集】頸部腫瘤の診かた
【特集】頸部腫瘤の診かた

腎と透析84巻2号
2018年2月増大号
【特集】腎と糖尿病:変革期の診断と治療
【特集】腎と糖尿病:変革期の診断と治療

小児内科48巻3号
2016年3月号
【特集】小児科医が担う思春期医療
【特集】小児科医が担う思春期医療

Modern Physician Vol.38 No.9
2018年9月号
【今月のアプローチ】内科疾患における生物学的製剤の使い分け
【今月のアプローチ】内科疾患における生物学的製剤の使い分け 日本に導入されて15年がたった生物学的製剤。いまだその使用に不安を感じる医師もいますが、本号特集ではエビデンスや事例を多数紹介しながら、製剤治療の最前線を伝えています。
さらに、代表的な製剤16種と現在開発中の生物学的製剤についても徹底的に分析。治療での有効性を高めるために役立つ一冊となっています。

臨床雑誌外科 Vol.80 No.10
2018年9月号
エビデンスからみた治療リスクの評価
エビデンスからみた治療リスクの評価 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

Heart View Vol.22 No.9
2018年9月号
【特集】心臓リモデリングをどう治すか 拡大心・肥大心へのアプローチ
【特集】心臓リモデリングをどう治すか 拡大心・肥大心へのアプローチ

関節外科 基礎と臨床 Vol.37 No.9
2018年9月号
【特集】大腿骨頚部・転子部骨折の手術 整復と内固定材の選択
【特集】大腿骨頚部・転子部骨折の手術 整復と内固定材の選択

看護管理 Vol.28 No.9
2018年9月号
特集 看護師長のための「地域分析」入門
特集 看護師長のための「地域分析」入門 地域包括ケアシステムが推進される中,病棟運営者である看護師長には「地域分析」の視点を持つことが求められています。入院患者の在宅移行にあたり迅速な医療・介護・福祉連携を考えるために,地域内の疾患の発症予防や健康増進に資するために,そして病院経営に貢献するために,「地域分析」は必須の視点・知識・スキルです。看護師長が病棟特性や地域の医療ニーズを分析し,各病棟で担うべき役割を考え,院内外と連携して新たなケアや必要となる仕組みを創出することが求められています。本特集では,地域医療機能推進機構(JCHO)本部が実施している看護師長研修をもとに,「地域分析」の具体的な手法を解説するとともに,実践事例を紹介します。

助産雑誌 Vol.72 No.9
2018年9月号
特集 早産と助産師のケア
特集 早産と助産師のケア 1950年代から低出生体重児の割合は年々増加傾向にあり,超低出生体重児や極低出生体重児の割合も増加しています。原因の1つとして高年妊娠が増えていることが挙げられますが,それ以外の原因を防ぐために助産師による予防的な介入はできないでしょうか。本特集では早産の原因を知り,助産師ができるケアとその実践をまとめています。関連記事として,「早産児と発達障害」および「低出生体重児の将来のリスク軽減」についての論考も紹介します。
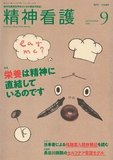
精神看護 Vol.21 No.5
2018年9月号
特集 栄養は精神に直結しているのです
特集 栄養は精神に直結しているのです 精神症状は薬を使って治すもの、というのがこれまでの常識でした。薬を否定するわけではありませんが、薬はあくまで対症療法。食事や生活環境により体質改善をした上に加えてこそ、薬は効果を現すのです。さらに、皆さんが持っている「栄養」の常識も疑う必要があるかもしれません。脳内神経伝達物質の元になるのはタンパク質ですが、現代の食事はタンパク質が不足し、代わりに糖質(炭水化物)が多すぎる傾向があります。それだけでなく、問題は腸なのです。腸管へのダメージで必要な栄養素を吸収できていないことが、私たちの心身に悪影響を与えている可能性があります。この特集は、患者さんを含め、私たち全員の心身の安定を目指す方法の1つに、「栄養への着目」があるのでは、という提案です。
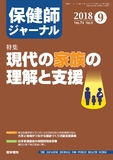
保健師ジャーナル Vol.74 No.9
2018年9月号
特集 現代の家族の理解と支援
特集 現代の家族の理解と支援 現代では,多様な価値観から家族の形や機能が変化し続けており,家族成員間の問題解決力が縮小している家族や健康の価値観の理解が難しい家族にしばしば遭遇する。そこで本特集では,改めて家族を理解するための諸理論や家族看護の実際を紹介し,現代の多様な家族への支援方法を考える。
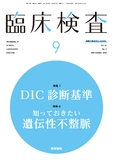
臨床検査 Vol.62 No.9
2018年9月号
今月の特集1 DIC診断基準/今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
今月の特集1 DIC診断基準/今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈 -

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 Vol.90 No.10
2018年9月号
特集 どこが変わった頭頸部癌診療ガイドライン
特集 どこが変わった頭頸部癌診療ガイドライン -

臨床眼科 Vol.72 No.9
2018年9月号
特集 第71回 日本臨床眼科学会講演集[7]
特集 第71回 日本臨床眼科学会講演集[7] -

臨床外科 Vol.73 No.9
2018年9月号
特集 癌手術エキスパートになるための道〔特別付録Web動画付き〕
特集 癌手術エキスパートになるための道〔特別付録Web動画付き〕 外科学において診療,教育,研究が重要であることは言うまでもない.そして診療の分野においては,医療倫理も含めた患者さんへの温かい対応,豊富な知識に基づいた適切また的確な判断,そして優れた医療技術は,それを支える大きな柱である.特に外科医においては,手術手技も含めた高度な技術によって,その診療は遂行される.一方,これらの手術技術の修得は,多くの先輩から後輩への指導とそれによる経験の蓄積,そして学術集会や論文,さらには手術見学などの機会を通した見聞によって,時を重ねつつ成し遂げられる.これら手術技術の修得を,より速やか,かつ着実に身に付ける方策を,自身の経験を通して,もしくは自身が展開する教育法などの観点から,各分野におけるエキスパートの先生に,若き前途洋々の外科医への提言をご執筆いただいた.本特集が,若き外科医もしくは若手外科医の教育に携わる先生方の「道標」となり,ひいてはわが国の外科医療のさらなる発展に寄与することを願うものである.

精神医学 Vol.60 No.8
2018年8月号
特集 作業療法を活用するには
特集 作業療法を活用するには -

脳神経外科 Vol.46 No.8
2018年8月号
-

公衆衛生 Vol.82 No.9
2018年9月号
特集 日本におけるWHO協力センター
特集 日本におけるWHO協力センター -
