
脳神経外科 Vol.46 No.7
2018年7月号
-

臨床婦人科産科 Vol.72 No.8
2018年8月号
今月の臨床 スペシャリストに聞く産婦人科でのアレルギー対応法
今月の臨床 スペシャリストに聞く産婦人科でのアレルギー対応法 -

臨床外科 Vol.73 No.8
2018年8月号
特集 徹底解説! 膵尾側切除を極める〔特別付録Web動画付き〕
特集 徹底解説! 膵尾側切除を極める〔特別付録Web動画付き〕 膵癌ばかりでなく,IPMNをはじめとした低悪性度腫瘍の手術件数が全国的に増加しつつあります.膵頭部病変には一般的に膵頭十二指腸切除が行われますが,体尾部病変に対する術式は膵切除範囲,リンパ節郭清,後腹膜組織の切除範囲,脾温存の有無など,バリエーションに富んでいます.切除範囲一つとっても,「尾側膵切除術」の中に「膵体尾部切除」「膵尾部切除」「脾温存膵体尾部切除」「腹腔動脈合併膵体尾部切除」などが含まれています.また最近では,腹腔鏡手術やロボット支援手術も導入されつつあります.本特集では,症例ごとに適切な術式を正確に行うため,解剖学的知識を深め,各術式の適応や長所・短所を理解できるよう,さまざまな視点から解説していただきました.研修医から一般・消化器外科医,さらにはこれから肝胆膵外科高度技能専門医をめざす若手外科医の診療の一助となれば幸いです.

総合診療 Vol.28 No.8
2018年8月号
特集 80歳からの診療スタンダード Up to Date
特集 80歳からの診療スタンダード Up to Date 超高齢社会において、診療ガイドラインをどのように考えて使いこなすかは重要な課題です。本特集では、特に80歳以上の高齢者に多いプロブレムについての診療ガイドラインを、高齢者の外来診療目線でまとめました。高齢者にとってのcommon diseaseのみならず、高齢者の意思決定、転倒、尿失禁など日常診療で重要なプロブレムを網羅! 高齢者の「病気を診る」のではなく、高齢者を「トータルに診る」ための一助に。

≪OS NEXUS 15≫
膝関節手術の落とし穴
陥らないためのテクニック
No.15では,大きく膝領域の手術を3つの章(膝靱帯再建術,半月板修復術,骨切り術)に分けて掲載。
手術適応,ポータルや骨孔の作製方法や位置,移植腱の作製と導入(靱帯),縫合法(半月板),プレートの固定法(骨切り術)といった手術進行を詳述していきながら,インプラントの設置不良や術後の合併症といった「落とし穴」に陥らないための回避方法と手術のコツを写真やイラストでわかりやすく解説。

成人病と生活習慣病48巻1号
2018年1月号
【特集】今日の結核
【特集】今日の結核

JOHNS34巻1号
2018年1月号
【特集】側頭骨疾患の困難症例-診断と治療のコツと工夫
【特集】側頭骨疾患の困難症例-診断と治療のコツと工夫

周産期医学48巻1号
2018年1月号
【特集】産科の薬物療法―update
【特集】産科の薬物療法―update

小児外科50巻1号
2018年1月号
【特集】胆道閉鎖症アップデート
【特集】胆道閉鎖症アップデート

小児内科50巻1号
2018年1月号
【特集】授乳と離乳─小児科医の基礎知識
【特集】授乳と離乳─小児科医の基礎知識

腎と透析84巻1号
2018年1月号
【特集】最近のバスキュラーアクセスの進歩とその合併症対策
【特集】最近のバスキュラーアクセスの進歩とその合併症対策

成人病と生活習慣病47巻12号
2017年12月号
【特集】手術を考慮する‘腹痛’の鑑別診断
【特集】手術を考慮する‘腹痛’の鑑別診断

消化器内視鏡29巻12号
2017年12月号
【特集】ここまでできるIEE
【特集】ここまでできるIEE

JOHNS33巻12号
2017年12月号
【特集】みみ・はな・のどの入口部病変
【特集】みみ・はな・のどの入口部病変
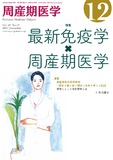
周産期医学47巻12号
2017年12月号
【特集】最新免疫学×周産期医学
【特集】最新免疫学×周産期医学

小児外科49巻12号
2017年12月号
【特集】小児急性胃腸炎・急性虫垂炎
【特集】小児急性胃腸炎・急性虫垂炎

小児内科49巻12号
2017年12月号
【特集】プライマリ・ケア医が知っておくべき小児悪性疾患
【特集】プライマリ・ケア医が知っておくべき小児悪性疾患

腎と透析83巻6号
2017年12月号
【特集】ここまで進んだ腎泌尿器疾患の画像診断
【特集】ここまで進んだ腎泌尿器疾患の画像診断
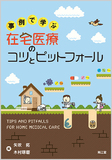
事例で学ぶ在宅医療のコツとピットフォール
設備や資材の不足、居宅で必要だった注意や心配り、患者・家族との行き違いなど…。在宅医療におけるピットフォール/反省事例を、経験豊富なエキスパートたちが分析。現場で役立つノウハウを導き出して提示する。事例共有の機会が少ない在宅医療において、教科書だけでは身につかない、実践に裏打ちされたコツと考え方を伝授する!

臨床雑誌外科 Vol.79 No.7
2017年7月号
TNM分類第8版を読み解く
TNM分類第8版を読み解く 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。
