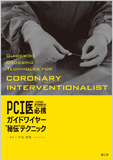
こうすれば必ず通過する!PCI医必携ガイドワイヤー”秘伝”テクニック
PCIにおけるガイドワイヤーの知識とその操作法について、エキスパートがその経験をもとに解説。PCI初級者・中級者・上級者のレベルごとに、様々な病変やそれに合ったガイドワイヤーの選択、実際の操作法、合併症への対応などを要点を押さえて詳述している。あらゆるPCI医のさらなる上達を目指した“秘伝”の一冊。

100症例に学ぶ小児診療
小児科診療で押さえておくべき、疾患の鑑別ポイント、ピットフォールを一挙収録!
主訴や症状の経過を的確に聞き出し、
重篤な疾患を見落とさず、適切に診断するコツを伝授
『日経メディカル』の名物企画“日経メディクイズ”から、小児疾患100症例を難易度別に厳選。小児診療の鑑別診断スキルを再確認するツールとして活用できます。日常診療で出会う頻度の高い疾患や、医師が判断を誤りやすい症例を使って、初診時の所見や症状の推移から、どのような疾患を鑑別疾患に挙げ、確定診断のためにどの検査を行うべきかを解説します。
取り上げるのは、帯状疱疹、ヒトメタニューモウイルス、新生児・乳児消化管アレルギー、QT延長症候群をはじめ、食物アレルギーによるアナフィラキシー、横紋筋融解症、溶血性尿毒症症候群など、迅速な診断・処置が必要なケース。その他にも、潜在性結核感染や血友病、ゴーシェ病など、頻度は高くないものの日常診療で見落としてはならない疾患も数多く掲載しています。
さらに、総論「外来診療における鑑別のポイント」では、小児患者の初診時における身体所見の取り方、重症例と軽症例の見分け方を提示します。

レジデントノート Vol.20 No.3
2018年5月号
【特集】X線所見を読み解く! 胸部画像診断〜読影の基本知識から浸潤影・結節影などの異常影、無気肺、肺外病変のみかたまで
【特集】X線所見を読み解く! 胸部画像診断〜読影の基本知識から浸潤影・結節影などの異常影、無気肺、肺外病変のみかたまで
葉間裂や肺縦隔境界線を含めた正常画像解剖,シルエットサインなど読影の前に知っておきたい基本知識から,異常影の性状・分布・随伴所見から考えられる病態・鑑別疾患を解説.CTの前に胸部X線を十分に読影しよう

国立がん研究センターに学ぶ がん薬物療法看護スキルアップ
国立がん研究センター中央/東病院 両看護部の総合力をもって企画・編集。がん薬物療法を専門とする医師、薬剤師、専門看護師、認定看護師が執筆し、がん薬物療法の治療と看護を系統的に解説。実践力を高めるためにさらなるスキルアップを目指す看護師だけでなく、はじめてがん薬物療法看護に携わる看護師にも必携の一冊。

臨床皮膚科 Vol.72 No.4
2018年04月号
-

看護研究 Vol.51 No.2
2018年04月号
特集 未来語りのダイアローグとオープンダイアローグ 看護研究における「開かれた対話」
特集 未来語りのダイアローグとオープンダイアローグ 看護研究における「開かれた対話」 -

総合リハビリテーション Vol.46 No.4
2018年04月号
特集 障害児の学校教育と学外活動
特集 障害児の学校教育と学外活動 在宅で生活している障害児がどのような日常生活を送っているのかということを,障害児を主な対象とする専門家を除けば,その他多くのリハビリテーション関係者は,実はよく知らないのではないでしょうか.しかし,18 歳以降に,例えば就労支援の場面などでかかわる機会はあり,それまでの生活について一定の共通認識を確立する必要性を感じます.学校に通う教育年齢の障害児を対象として,日中活動の大半を占める学校での活動と学校以外での活動について,現状と課題を明らかにすることを目的に本特集を企画しました.

理学療法ジャーナル Vol.52 No.4
2018年04月号
特集 変形性膝関節症に対する最新の保存療法
特集 変形性膝関節症に対する最新の保存療法 変形性膝関節症に対する理学療法は,これまで人工膝関節置換術を代表とする重症度の高い患者に対する手術後のかかわりが中心となってきた.その結果,現在では安定した臨床成績を得ることが可能となったが,保存的な理学療法に関してはここ数十年,大きな発展はなかったと考えている.今後,理学療法士が行うべきことは,重症度の低い患者に対するアプローチであり,古典的な理学療法からの脱却が早期に求められている.本特集では,その方向性を解説いただいた.

論文を正しく読むのはけっこう難しい
診療に活かせる解釈のキホンとピットフォール
ランダム化比較試験には実に多くのバイアスや交絡因子が潜んでいる。“結果を出す”ために、それらはしばしば適切に処理されない、あるいは確信犯的に除去されない。一方で、臨床研究を行う際の規制は年々厳しさを増している。臨床研究の担い手として、実施する側のジレンマも熟知した著者が、それでもやっぱり見逃せない落とし穴を丁寧に解説。本書を読めば、研究結果を診療で上手に使いこなせるようになる!

検査と技術 Vol.46 No.5
2018年05月号
-

生体の科学 Vol.69 No.2
2018年04月号
特集 宇宙の極限環境から生命体の可塑性をさぐる
特集 宇宙の極限環境から生命体の可塑性をさぐる -

BRAIN and NERVE Vol.70 No.4
2018年04月号
増大特集 Antibody Update 2018
増大特集 Antibody Update 2018 2013年4月号増大特集でAntibody Updateを取り上げた。それから5年が経ち,自己抗体研究はさらに進歩がみられている。本特集では前回の増大特集の内容から新たに加わった知見を盛り込み,それぞれの自己抗体の持つ意義や治療などについて各分野のエキスパートに執筆いただいた。

胃と腸 Vol.53 No.4
2018年04月号
主題 腸管感染症 最新の話題を含めて
主題 腸管感染症 最新の話題を含めて -
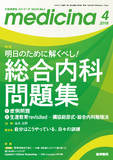
medicina Vol.55 No.5
2018年04月号
特集 明日のために解くべし!総合内科問題集
特集 明日のために解くべし!総合内科問題集 本特集は人気執筆陣による日常診療に役立つ「Part 1 症例問題62問」と「Part 2 獨協総診式・総合内科勉強法」の2部構成となっている。内科領域から幅広く出題された良問を解きながら、勉強法を実践することで、知識のアップデート、臨床力アップに最適な1冊。総合内科専門医試験を受験される方にもお勧めしたい。

medicina Vol.55 No.4
2018年04月号 (増刊号)
プライマリ・ケアでおさえておきたい重要薬・頻用薬
プライマリ・ケアでおさえておきたい重要薬・頻用薬 -

Gノート Vol.5 No.3
2018年4月号
【特集】何から始める!? 地域ヘルスプロモーション 研修・指導にも役立つ ヒントいっぱいCase Book
【特集】何から始める!? 地域ヘルスプロモーション 研修・指導にも役立つ ヒントいっぱいCase Book 「地域ヘルスプロモーションって実際何をどうすればいいの?」そんなお悩みをおもちの方必見!本特集では具体的なCaseから,実践の工夫やヒントが理論と共に学べます.研修や指導,ポートフォリオ作成にも最適!

成人病と生活習慣病47巻9号
2017年9月号
【特集】関節痛をどう診るか
【特集】関節痛をどう診るか

腎と透析83巻3号
2017年9月増大号
【特集】AKI診療の進歩2017
【特集】AKI診療の進歩2017

消化器内視鏡29巻9号
2017年9月号
【特集】これでわかる! 食道胃接合部疾患
【特集】これでわかる! 食道胃接合部疾患

小児内科49巻9号
2017年9月増大号
【特集】診療の「コツ」を伝える─先輩からのアドバイス
【特集】診療の「コツ」を伝える─先輩からのアドバイス
