
小児外科49巻9号
2017年9月号
【特集】腎をもっと知る
【特集】腎をもっと知る

周産期医学47巻9号
2017年9月増大号
【特集】ちょっと気になる新生児―お母さんの不安に答える
【特集】ちょっと気になる新生児―お母さんの不安に答える

JOHNS33巻9号
2017年9月増大号
【特集】頭頸部悪性腫瘍の疑問に答える
【特集】頭頸部悪性腫瘍の疑問に答える

看護管理 Vol.28 No.4
2018年04月号
特集 新任看護師長必読! 変化の時代を生き抜く 人と組織のレジリエンス
特集 新任看護師長必読! 変化の時代を生き抜く 人と組織のレジリエンス 毎春の「新任看護師長必読」企画として,本年は「レジリエンス」を取り上げます。病棟にはさまざまな診療科の患者が入り乱れ,退院支援や地域連携の体制づくりは喫緊の課題です。組織の在り方も診療報酬の体系も目まぐるしく変わり,看護の仕事をめぐる変化のスピードはどんどん速くなっています。現場をリードする看護管理者に求められる役割も増え,ストレスやプレッシャーに心が折れそうになることもあるでしょう。そのような中で,「変化や困難に向き合い,乗り越え,適応する力」として,「レジリエンス」という概念が注目されています。本特集では,変化の時代を生き抜くための個人と組織の「レジリエンス」について,考え方を整理するとともに,その高め方を提示します。特に,問題解決過程(PDP)を共通言語に組織としてのレジリエンスを高めるための実践を紹介します。

助産雑誌 Vol.72 No.4
2018年04月号
特集 産科混合病棟の中で助産師にできること
特集 産科混合病棟の中で助産師にできること 少子化を背景に,産科病棟の混合化が進行しています。日本看護協会が2016年に行なった調査では,8割近い施設が産科混合病棟であるという結果が示されました。産科混合病棟の何よりの問題点は,安全で安心な出産環境の確保が難しくなることでしょう。助産師が他科患者を受け持つことで,妊産褥婦へのケア提供に専念できない状況があります。本特集では,産科混合病棟の現状について,最新のデータを示しながらその問題点や課題を解説していただきます。また,実際に産科混合病棟で働く管理者の方々に,自施設の現状や課題,それらとどう向き合い乗り越えてきたのかについてご紹介いただくことで,日常臨床における課題を解決するためのヒントを得たいと思います。

訪問看護と介護 Vol.23 No.4
2018年04月号
特集 死を前にした人に私たちができること 現場の語りと事例から考える
特集 死を前にした人に私たちができること 現場の語りと事例から考える
超高齢多死時代では、住み慣れた自宅で、人生の最終段階を迎えた人と誠実に関わることが求められます。では、まもなくお迎えが来る人に、どのように関わるとよいのでしょう。単なる励ましが通じない看取りの現場にあって、一部のエキスパートだけではなく、関わるすべての人が、「自分がその人に何ができるか」を言葉にできるでしょうか? たとえ無力感を覚えながらも、その場に居続けられるのでしょうか?
本特集では、書籍『死を前にした人にあなたは何ができますか?』(医学書院)で紹介されている「苦しむ人への援助と5つの課題」を活用して、実践者たちの事例をご紹介します。個人で、ステーション全体で、多職種で、看取りに対する苦手意識に向き合っていきましょう。

保健師ジャーナル Vol.74 No.4
2018年04月号
特集 データヘルス新時代
特集 データヘルス新時代 第2期データヘルス計画がスタートに伴う保険者インセンティブの本格導入や,介護保険事業(支援)計画におけるデータに基づく課題分析の要請など,保健活動が大きく変わろうとしている。今後,保健師がどのようにデータヘルスに取り組んでいくか,事例を踏まえながら考える。

看護教育 Vol.59 No.4
2018年04月号
特集 問題解決志向に疲れたら……
特集 問題解決志向に疲れたら…… -

手順が見える! 次の動きがわかる!
消化器外科の手術看護
オペ室看護は“覚える”だけでは物足りない。必要なのは、手術の流れを理解し、進行状況を把握し、次を予測する力だった!「胃の摘出範囲は何で決まる?」「肝臓切除が時間との闘いなのはなぜ?」―今さら聞けない“?”に答えながら、よくある10種類の手術のキモとヤマ場を解説。この1冊で、手術がもっと好きになる!

臨床検査 Vol.62 No.4
2018年04月号(増刊号)
疾患・病態を理解する 尿沈渣レファレンスブック
疾患・病態を理解する 尿沈渣レファレンスブック -

病院 Vol.77 No.4
2018年04月号
特集 病院が直面する「すでに起こった未来」
特集 病院が直面する「すでに起こった未来」 急速な少子高齢化に伴う地域の傷病構造の変化は,病院に中期的な経営戦略を持つことを要請している。ドラッカーは,こうした変化に対応するために「すでに起こった未来」に気づくこと,それをもとに自組織の経営戦略を検討することの重要性を指摘する。本特集では,わが国の医療界における「すでに起こった未来」に目を向け,今後の課題を考える視点を読者に提供する。
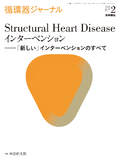
循環器ジャーナル Vol.66 No.2
2018年04月号
Structural Heart Diseaseインターベンション 「新しい」インターベンションのすべて
Structural Heart Diseaseインターベンション 「新しい」インターベンションのすべて -

脳神経外科 Vol.46 No.3
2018年03月号
-

総合診療 Vol.28 No.4
2018年04月号
特集 感染症外来診療「賢医の選択」 検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
特集 感染症外来診療「賢医の選択」 検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか? 本特集では、感染症を専門とはしない臨床医でも賢い判断「Choosing Wisely」ができるよう、第一線の感染症エキスパートに、臨床的に重要な検査と内服薬について、また感染症予防に重要なワクチンについても、その適用を中心に「賢医がどのような選択をするか」という視点から、使い方を伝授してもらいます!

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 Vol.90 No.4
2018年04月号
特集 基本診察・処置・手術のABC
特集 基本診察・処置・手術のABC -

臨床眼科 Vol.72 No.4
2018年04月号
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2] -

臨床婦人科産科 Vol.72 No.3
2018年04月号
今月の臨床 ここが知りたい!早産の予知・予防の最前線
今月の臨床 ここが知りたい!早産の予知・予防の最前線 -

臨床外科 Vol.73 No.4
2018年04月号
特集 機能温存と機能再建をめざした消化器外科手術 術後QOL向上のために
特集 機能温存と機能再建をめざした消化器外科手術 術後QOL向上のために 近年の基礎的研究および診断・治療技術の進歩により,外科治療についても必要十分であり,かつより低侵襲な手術を行うという考え方のもとに医療が展開されています.しかし低侵襲手術であれ縮小手術であれ,外科手術では何らかの(または幾許かの)機能の喪失は避けられないことも事実です.そのため外科医には,手術による機能の低下を最小限に留めること,その機能を可及的に再建することが,術後の患者のQOLの点からも強く求められています.本特集では,患者の術後QOLの面から,まず総論で生理学的および統計学的評価法を解説し,各論では各術式における機能温存もしくは機能再建法に関して,その適応,治療のコツ(動画も含めて),結果について解説していただきました.

脳卒中病態学のススメ
本書は第一線の執筆陣により最新の知見や研究方法をまとめ,これから脳卒中研究を始める医師にとってバイブルとなる一冊となっている.さらに,病態を網羅していることにより,研究者だけではなく臨床家にも役立つハイブリッドな内容となっている.

日経DIクイズ 精神・神経疾患篇
うつ病、不眠症、統合失調症、認知症、パーキンソン病、てんかん、頭痛
精神・神経7疾患の服薬指導、疑義照会に生かせる実践的な事例が満載!
"患者さんに余計なことを言ってしまわないか不安で、薬を手渡すだけに終始してしまう"──。
うつ病や統合失調症など、精神疾患患者に対する服薬指導に悩む薬剤師は多い。
精神・神経疾患の病態生理と治療指針の「基本」を学んで、その服薬指導や疑義照会のコツを、クイズ形式で理解を深めていきます。「日経ドラッグインフォメーション」本誌に掲載した日経DIクイズから、精神・神経疾患に関するクイズを再編集し、現状に則してアップデートしています。
患者と対面する薬局薬剤師にとって、学びがいのあるケーススタディを収載しています。
【主な内容】
●精神・神経疾患の基礎知識と処方の実際
(うつ病、不眠症、統合失調症、認知症、パーキンソン病、てんかん、頭痛)
●日経DIクイズ 50題(書き下ろし含む)
●医師が語る 処方箋の裏側 15本
●精神疾患患者とのコミュニケーションのコツ
