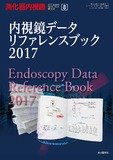
消化器内視鏡29巻8号(増大号)
2017年8月増大号
内視鏡データリファレンスブック2017
内視鏡データリファレンスブック2017

周産期医学47巻8号
2017年8月号
【特集】超早産児の予後向上のための戦略【2】
【特集】超早産児の予後向上のための戦略【2】

JOHNS33巻8号
2017年8月号
【特集】耳鼻咽喉科疾患と生活指導-予防とセルフケア
【特集】耳鼻咽喉科疾患と生活指導-予防とセルフケア

小児内科49巻8号
2017年8月号
【特集】子どもの眠り
【特集】子どもの眠り

小児外科49巻8号
2017年8月号
【特集】小児にかかわる診療ガイドライン
【特集】小児にかかわる診療ガイドライン

精神看護 Vol.21 No.2
2018年03月号
特集 オープンダイアローグ 対話実践のガイドライン/精神科で看取るために必要な技術と考え方(前編)
特集 オープンダイアローグ 対話実践のガイドライン/精神科で看取るために必要な技術と考え方(前編) 患者さんの高齢化に伴い、精神科でも看取りのケースが増えてきました。この特集は精神科で看取るとはどういうことなのかを、一から考えてみようという企画です。前編となる今回は、緩和ケアと精神科の両方を経験してきた松谷典洋さんに、看取りの技術を上げるために抑えておきたい基礎的な部分を解説していただきます。そして精神科でのより良い看取りを目指して試行錯誤をされてきた小貫洋子さんに、その経験を伝えていただきます。

理学療法ジャーナル Vol.52 No.3
2018年03月号
特集 理学療法における動作のアセスメント
特集 理学療法における動作のアセスメント 動作のアセスメントは,観察や分析結果をもとに,機能評価による裏づけを考え,動作を論理的に解釈し,検討することまでが含まれる.アセスメント対象となる動作は無数にあり,対象者の病態・年齢層も多様である.健常動作との比較だけではアセスメントは成立しない.動作のアセスメントは何に着目しどのように進めるのか,を命題に,高齢者・日常生活活動・速度因子の重要性・見えない阻害因子「痛み・心理要因」を取り上げ,「動作」の成因とともに多面的に考え,解説していただいた.

検査と技術 Vol.46 No.4
2018年04月号
-

総合診療 Vol.28 No.3
2018年03月号
特集 糖尿病のリアル 現場の「困った!」にとことん答えます。
特集 糖尿病のリアル 現場の「困った!」にとことん答えます。 糖尿病患者数は増え続け、なかでも高齢患者の増加は、患者の抱える問題の多様化・複雑化をもたらしています。治療薬が増えたことは、よい面もある一方で、治療方針の立てにくさにもつながっています。超高齢社会における糖尿病診療のさらなる課題について、現場のリアルな「困った!」に糖尿病専門医がとことん答えました。
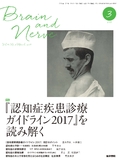
BRAIN and NERVE Vol.70 No.3
2018年03月号
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く 『認知症疾患診療ガイドライン2017』が2017年8月に出版された。得てしてとっつきにくい印象を持たれがちなガイドラインだが,本特集ではこのたび改訂された本ガイドラインの背景やガイドラインの中では説明しきれなかった点などを紹介し,ガイドラインを立体的に読み解くためのガイドとして企画した。はからずも,本ガイドラインにしみ込んだ作成者たちの意気込みと本音までが感じられる内容となっている。

臨床皮膚科 Vol.72 No.3
2018年03月号
-

臨床婦人科産科 Vol.72 No.2
2018年03月号
今月の臨床 ホルモン補充療法ベストプラクティス いつから始める?いつまで続ける?何に注意する?
今月の臨床 ホルモン補充療法ベストプラクティス いつから始める?いつまで続ける?何に注意する? -
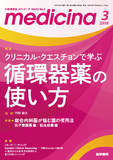
medicina Vol.55 No.3
2018年03月号
特集 クリニカル・クエスチョンで学ぶ 循環器薬の使い方
特集 クリニカル・クエスチョンで学ぶ 循環器薬の使い方 循環器疾患を総合内科で診ることは多い。高血圧・脂質異常症・心房細動・心不全などのcommon diseaseの薬物療法では適切な治療・管理のために薬の知識が必要となるが,エビデンスは次々に蓄積あるいは変化し,新薬も多く難解である。本号では,クリニカル・クエスチョン形式で循環器薬の疑問・悩みを明確に示し,要点を読み解きやすくまとめた。

看護教育 Vol.59 No.3
2018年03月号
特集 私たちのストレスケア
特集 私たちのストレスケア -

希望をくれた人
パラアスリートの背中を押したプロフェッショナル
パラアスリート(障害者アスリート)の背中を押し、支えてきたプロフェッショナルの言葉と選手の述懐を通して、その真摯な姿を浮き彫りにした新しいスポーツノンフィクション。

精神医療は誰のため?
ユーザーと精神科医との「対話」
ユーザーと精神科医の間には大きなギャップがある。それでもよりよい医療・支援を実現したいという思いは共通である。双方が場を共にし様々な問題を話し合った貴重な記録。

どうして普通にできないの!
「かくれ」発達障害女子の見えない不安と孤独
違和感を抱えながら普通になろうと必死に努力しては失敗を重ね、大人になってやっと「発達障害」という理由を得た一人の女性の手記。わかりにくい障害の理解のために。

リハビリテーション・エッセイ
砂原茂一さんの『リハビリテーション』を読む
遠いビジョンを読み直す
我が国のリハビリテーション創世期に執筆された歴史的な名著に、高次脳機能障害をもつ当事者が真正面から向き合い、本音を綴り、さらにイラストを描く。リアルなリハビリテーション論。

リハビリテーション・レポート
「認知運動療法」日記
ボクは日々、変容する身体
高次脳機能障害の当事者が絵日記風に綴る、1年間にわたる「認知運動療法」体験記。リハビリが進むにつれて失われた自分の身体を再発見していく過程を生き生きと描き出す。

≪リハビリテーション・コミック≫
リハビリテーション・コミック
「のーさいど」から
脳がこわれてもボクは漫画家!
右脳を広範囲に損傷した著者が、リハビリテーションを経てコミック作家デビューを果たした作品。障害をもつ当事者の目線から描かれた、高次脳機能障害のサーバイバル。
